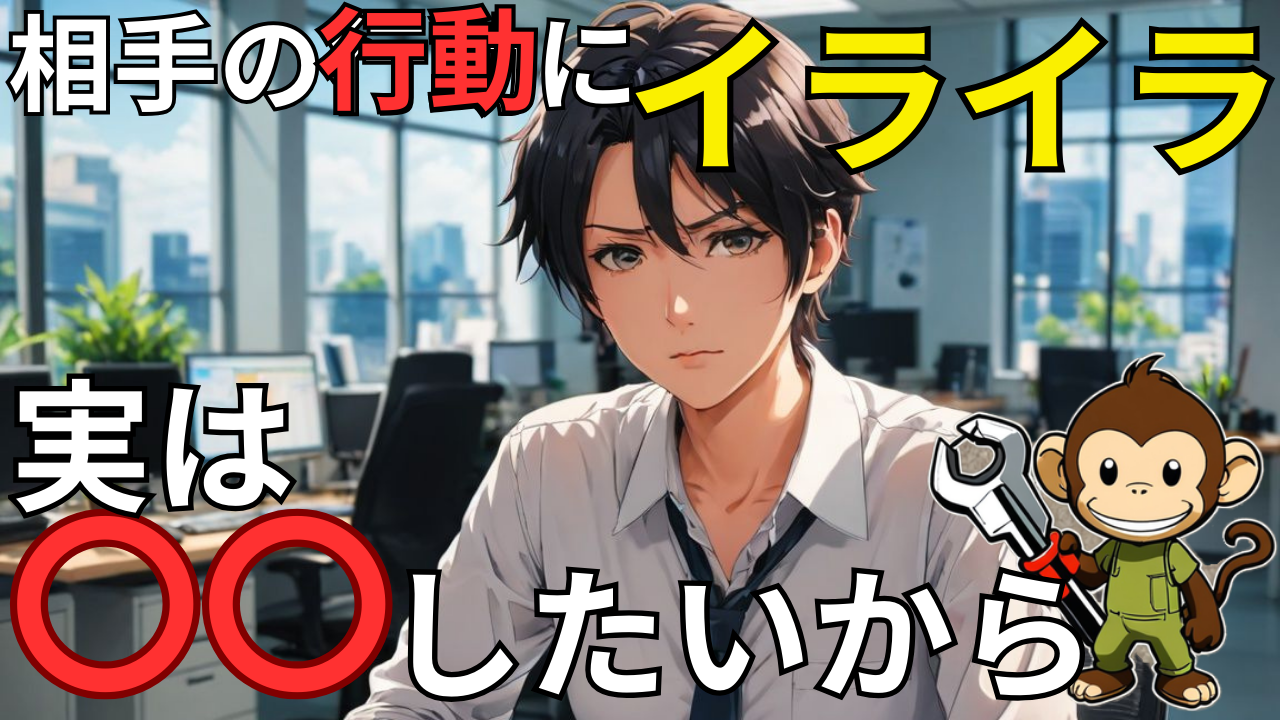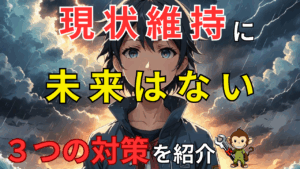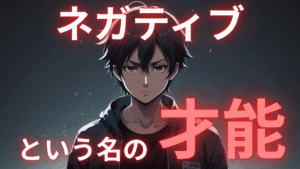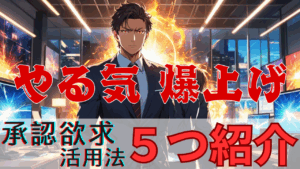やめれば他人に左右されない強いメンタルが育つ
人の行動にイライラしてしまう…そんな経験、誰にでもありますよね。
「なんであの人はあんなことをするんだろう」「もっとこうすればいいのに」と思えば思うほど、気持ちが乱れてしまう。
実はその裏には、「相手をコントロールしたい」という心理が隠れています。
ですが、自分の意識を少し変えるだけで、イライラやストレスを減らすことができます。
更にその結果、他人に左右されない 強いメンタル が育っていきます。
今回は 「相手の行動にイライラするのは支配しようとしているから」 というテーマでお話します。
理由と3つの対策も紹介しますので、日々のイライラを減らして、心に余裕のある毎日を手に入れていきましょう。
【関連動画】
記事と同様の内容が動画でも見られます。取り組みやすい方をお選びください。
【理由】なぜ相手の行動にイライラしてしまうのか
まずはなぜ相手の行動にイライラしてしまうのか「原因やデメリット」について簡単に話していきます。
1.不安だから支配してコントロールしたい
相手の行動にイライラするのは、「自分の思い通りに動かして安心したい」という支配欲が働いているからです。
私たち人は先の展開が見えないと、不安を感じます。
たとえば、部下が期限ギリギリまで動かないと、上司としては「本当に間に合うのか?」と不安になります。だからこそ、「早くやれ!」と強く指示したくなり、思い通りに動かないとイライラしてしまいます。
また、自分ならできることを相手ができないときも同じです。「これくらいできるはずなのに」という期待があるからこそ、動かない相手を見るとイライラしてしまうのです。
つまり、相手にイライラするのは「支配したい」から。でもその本質は「未来が見えず、不安を感じている」という気持ちの表れということです。
2.支配しようとするとメンタルが弱くなる
相手を支配しようとすると、メンタルは逆に弱くなってしまいます。
なぜなら、人はそれぞれ価値観や事情を持っており、相手は自分の思い通りには動いてくれないからです。
たとえば、家族に「もっとしっかりして」と何度も言っても、相手がその通りに動いてくれるとは限りません。むしろ反発されて、余計にイライラしてしまうこともあります。そのとき「なぜ分かってくれないのか」という不満が溜まり、不安が増幅していきます。
つまり、相手を支配しようとすればするほど、現実とのギャップに苦しみ、不安とストレスが積み重なっていきます。これは相手の行動で自分の心が左右されているということ。だからメンタルはますます弱くなっていきます。
3.「コントロールできる範囲」に集中する習慣
ではどうすれば良いのかですが、不安やイライラを減らしてメンタルを強くするためには、自分がコントロールできる範囲に意識を集中すれば解決します。
不安の多くは「自分ではどうにもならないこと」に執着することで生まれます。相手の行動や言葉、社会の状況などは自分ではどうにもならないことです。
たとえば、職場で同僚がだらだらしていることにイライラするよりも、「自分は今できる仕事に集中しよう」と切り替える。
こうして自分が「コントロールできる範囲」に意識を集中する習慣にする。こうすれば相手の行動に左右されることはなくなり、メンタルが強くなります。
ただ職場で後輩や部下に教育しないといけない場合もあるでしょう。どうしても相手を何とかして動かしたい。そんな時の対策も最後に紹介しています。
なぜ相手の行動にイライラしてしまうのかの「原因やデメリット」は以上です。
【やり方】支配をやめる「3つの対策」
ここからはイライラしない、支配をやめる「3つの対策」について話していきます。
1.範囲を明確にする
まずは、自分がコントロールできる範囲とできない範囲をはっきりさせましょう。
相手に口を出しすぎると、反発し、こちらはイライラする。この悪循環を避けるために「ここからは相手の範囲」と線を引く。
そして自分が「コントロールできる範囲」に集中することで、相手に左右されず感情をコントロールできます。
具体的やり方
- 相手に任せる部分を明確にする
- → 例:相手が担当する資料作りは任せ、自分は相談が必要なときだけ意見を出す
- 自分が干渉すべきでないことを意識する
- → 例:相手の業務の進め方には口出しせず見守る
- 相手の意思や、やり方を尊重する
- → 例:進め方を相手に任せて、必要なサポートだけする
- 自分ができる範囲に集中する習慣を作る
- → 例:自分の業務で優先順位を毎日3つ決める習慣にするなど
ポイント
「相手に任せる」「信用する」こと。口を出したがるのは相手のためではなく、自分が不安だからと自覚しましょう。
効果(C15)
僕の場合の例ですが、、後輩の仕事の進め方に口を出さず、「ここは任せよう」と決めるようにしました。最初はもどかしさもありましたが、気づくと無駄なイライラが減り、チーム内の雰囲気も良くなり、僕も後輩も仕事が前より上手くまわるようになりました。
2.期待値を調整する
相手に完璧を求めず、自分の期待値を調整してみましょう。
自分の理想を相手に求めると、現実とのギャップが発生してイライラしてしまいます。
ですが自分の期待値を相手に合わせて調整すれば、過度な期待をすることが無くなります。
具体的やり方
- 相手の状況や経験に応じて期待値を設定する
- → 例:完璧を求めず、「50点で十分」とする
- 完璧よりも前進や改善を重視する
- → 例:資料の出来が悪くても、納期は守ったからOKとする
- 小さな改善や努力を認める
- → 例:少し工夫した作業は「ここいいね」と声をかける
ポイント
「できて当たり前と思わない」こと。当たり前って、実は完璧主義に近い考え方です。人は意外と気付かないうちに期待値をどんどん上げてしまうので、一度基準を見直してみましょう。
効果(C15)
僕の場合の例ですが、後輩に対して「会社に来て何かしてるだけで十分」と期待値を調整したところ、「自分で考えて動いてるのはすごい」「思ったより出来てる!」と、むしろ喜ぶことになりました。
3.できる範囲で良い影響を与える
どうしても相手を何とかして動かしたい。そんな時は相手を支配しようとせず、自分が「できる範囲で良い影響」を与えることに意識を向けましょう。
無理にコントロールしようとすると、相手は嫌な気持ちになり反発しやすくなります。ですので「命令といった支配」ではなく、「良い影響を与える」ことで自然と導くことができます。
具体的やり方
- 相手の意見や相談を真摯に聞く
- → 例:困っている時は、まず最後まで話を聞き理解を示す
- 自分の考えは一度だけ簡潔に伝える
- → 例:自分の意見は短く要点を伝え、押し付けない
- 自分ができる良い行動を行う
- → 例:サポートできる部分を率先して行う。相手の行動を邪魔する要因を排除する。
- 少しでも協力的な行動を褒める
- → 例:相手が進めた作業や工夫を見つけて「ここ助かったよ」と伝える
- 皮肉や批判は言わない
- → 例:改善点があっても指摘しない。相手がアドバイスを求めた時のみ伝える。
ポイント
「影響を与えるだけ」ということ。そこから先の選択は「相手の範囲」です。だから変わらなくても相手を責めず、自分ができることだけに集中しましょう。
効果(C15)
僕の場合の例ですが、共用デスクを汚したままの同僚に「ちゃんと片付けて」と他の人が言っても、相手は「めんどくさいし、それくらいいいだろ」と言って終わりでした。でもフキンやごみ箱、ティッシュをデスクのそばに用意して陰ながらやりやすいようにサポートしてみたら「めんどくさい」が無くなり、自然と片づけてくれるようになっていました。
まとめ
「相手の行動にイライラするのは支配しようとしているから」というテーマ、いかがでしたか?
相手の行動に振り回されるのは、不安から「思い通りにしたい」と考えてしまうからです。けれど、その支配欲は余計なストレスを増やし、メンタルを弱くしてしまいます。
今回ご紹介した3つの対策。
- 境界線を明確にして、相手の範囲に踏み込まず、任せる部分は任せる
- 期待値を調整して完璧を求めず、小さな改善や努力を認める
- 支配ではなく、相手に良い影響を与えることで自然と変わるように導く
これらを日常に取り入れることで、イライラは減り、不安も小さくなり、強いメンタルが育つ。
そして人間関係はもっと穏やかで心地よいものになります。
ぜひ今日から、支配をやめて「自分がコントロールできる範囲に意識を集中する習慣」を始めてみてください。
関連記事
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の整備で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。