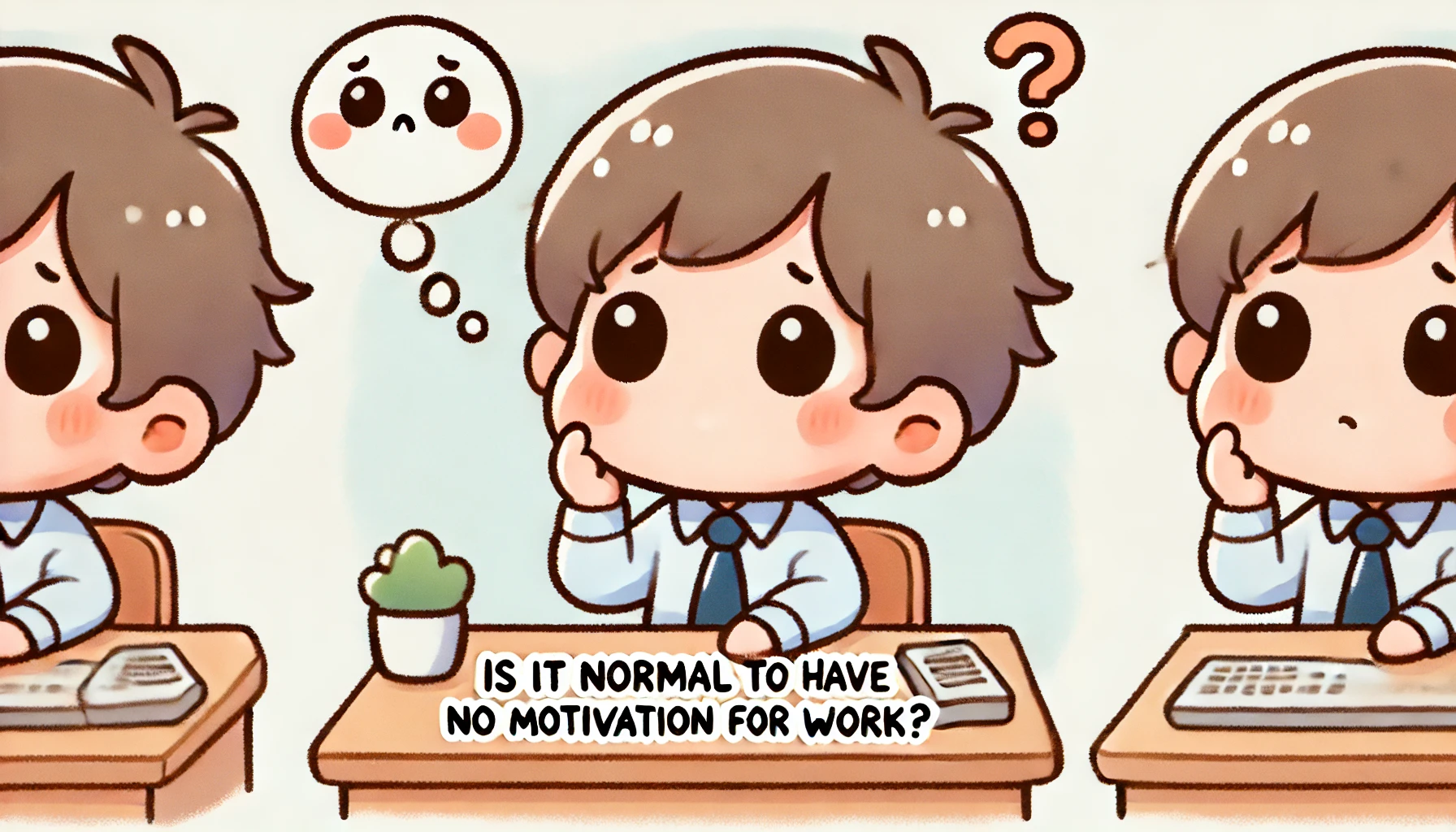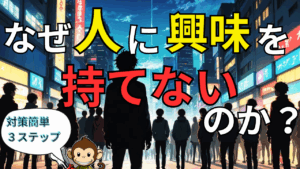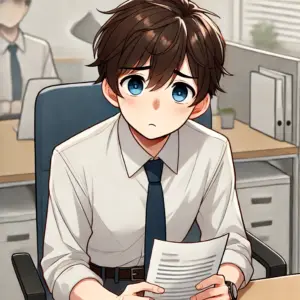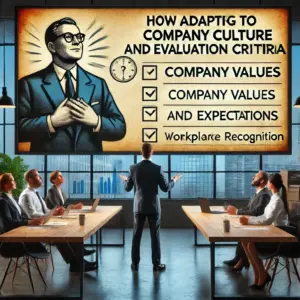モチベーションが上がらず憂鬱になりがちなあなたへ
「朝から仕事に行く気がしない」
「仕事が単調すぎてモチベーションが上がらない」
「人間関係のストレスでやる気がなくなる」
仕事や普段の生活でもやる気が出ない、覇気がない、だるい、なぜ他の人はやる気に満ち溢れているのに自分はこんなにやる気が出ないのだろうと悩んでしまう。特に内向的な性格や感覚的な部分が強い人にとってはこの問題が大きなストレスになることも。だけど、少し工夫をすることで、こうした悩みを解消することができるかもしれません。
私自身も昔からやる気がなく、長年こんな自分が嫌いになってしまっていました。
そんな自分を嫌って生きづらくと感じていた私が、人生は楽しいと考えられるようになった考え方の一つを紹介します。
この記事を読むことで、 「仕事にやる気が出ないのは当たり前」「やる気がなくても仕事は進められる」「そのための方法がある」 という考えを得ることができます。
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして職場の人間関係で悩み苦しみ、辛かった思いをしてきました。
ですが記事にある対策などを実施することで、現在はやる気が無くてもサクサク仕事をこなせるようになり、やる気が出ないと自分を責めていたストレスを軽減できるようになったほか、仕事も好調で、ほかっといてもやる気が出てくるようになり、以前より人生が楽しく思えるようになりました。
この記事では、「仕事のやる気がない」と感じる読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
結論:「やる気がなくてもOK!大事なのは付き合い方」
やる気には波があって当然で、いつも高いモチベーションを保てる人なんていません。
「やる気が出ない自分はダメだ」と責める必要はまったくなく、むしろその状態とうまく付き合っていくことこそが大切です。
実際、やる気がなくても、工夫次第で仕事を進めることはできますし、集中力や効率を上げることも可能です。
気分に左右されずに行動できる仕組みを持つことが、安定した毎日をつくるカギになります。
「やる気がない=自分がダメ」ではなく、
「やる気がないときにどう過ごすか?」を考えることが、本当の意味での成長につながるのです。
原因・根拠:「仕事のやる気が出ないのは当たり前な理由」

① 人間は常にモチベーションを維持できる生き物ではない
人間のモチベーションは一定ではなく、状況や時間の経過とともに変動することが多くの研究で示されています。
楠奥繁則 (2004)によると「自ら進んで何かをする」とき,「楽しい」とき,脳では快適感情をもたらすドーパミンと,注意・集中・怒り・怯えといった感情をもたらすノルアドレナリンが分泌されていると言われています。
そしてこのドーパミンとノルアドレナリンがモチベーションの正体であると考えられています。ですので「自ら進んで何かをする」とき、「楽しい」とき以外ではモチベーションは上がらないのが私たち人間にとって自然なことと考えられます。
①ドーパミン:やる気のエンジン
働きの仕組み
ドーパミンは脳の「側坐核(そくざかく)」や「前頭前皮質」などで分泌され、目標に向かって行動する力に関わると言われています。
役割:ドーパミンは「報酬系」の神経伝達物質です。
→「やったら得する」「達成したら嬉しい」という期待感・快感を生みだすと言われています。
②ノルアドレナリン:集中力と緊張感のスイッチ
働きの仕組み:ノルアドレナリンは主に「青斑核(せいはんかく)」から放出され、 注意力や覚醒状態を高めることで、目標への集中力や実行力を強化すると言われています。
役割:ノルアドレナリンは「覚醒」「注意」「ストレス応答」に関わる神経伝達物質です。
→特にプレッシャー下での集中や即応性に大きな影響を与えると言われています。
ノルアドレナリンの分泌が強くなるにつれ,覚醒→注意→集中→恐怖→闘争→怒り,の順に感情が変化していくと言われており、「集中」のレベルならノルアドレナリンも効果的だが,「恐怖」のレベルになると健康に害を及ぼすことになると考えられています。
💡 補足メッセージ:
例えば締め切りギリギリで仕事を完成させるべく取り組んでいる状態、危険な作業をしている状態などは、ノルアドレナリンの影響で「集中」し、モチベーションが上がり仕事をしていると考えられますが、逆にもう間に合わないと「恐怖」しモチベーションが下がり、ストレス過多となってしまう可能性が考えられます。
参考:楠奥繁則 (2004)。 職場におけるストレス・マネジメントの探究.立命館経営学, 42 (6), 115-133.
https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/record/694/files/be42_6kusuoku.pdf
② モチベーションが低下してしまう理由
モチベーションとは、目標や目的などの要因に対して行動を起こし、達成するまで持続させる過程や機能を指します。動機づけとも呼ばれ、心理学の分野では「外発的動機付け」と「内発的動機付け」などに分けられています。
この動機づけが行われていないとモチベーションは低下してしまうと考えられます。
内発的動機付け
- 「自分の内側から湧いてくるやりたい気持ち」が原動力
- 例:好奇心、楽しさ、達成感、自己成長への欲求
外発的動機付け
- 「外から与えられる報酬や評価」が原動力
- 例:お金、称賛、昇進、怒られたくない、褒められたい
人の3つ欲求
上記動機づけの理由として、人の欲求があります。そして欲求を分類する上で、一般的にもよく知られているものでA.H. マズロー(A.H.Maslow)の欲求階層説と呼ばれるものがあります。人の欲求は 5 つの階層から構成されているというものですが、そこから更に修正したモデルがC.P. アルダーファ(1972)の ERG モデルと呼ばれる3つの欲求になります。
| ERG分類 | 説明 | 対応するマズローの欲求階層 | 備考(動機づけの傾向) |
|---|---|---|---|
| 生存欲求(Existance) | 生理的・安全に関する基本的な欲求 | 生理的欲求、安全欲求 | 外発的になりやすい |
| 関係欲求(Relatedness) | 他者との関係性を求める欲求 | 社会的欲求 | 対人関係の満足によるモチベーション |
| 成長欲求(Growth) | 自分自身の成長や達成、自己実現を求める欲求 | 尊厳欲求、自己実現欲求 | 内発的が中心 |
- 生存欲求(Existance)
欲求階層説でいう下記に該当- 生理的欲求(食べたい、寝たい)←外発的になりやすい
- 安全欲求(安心して暮らしたい)←外発的も内発的もあり
- 関係欲求(Relatedness)
他者との関係を構築し維持したいというもので、欲求階層説でいう下記に該当- 社会的欲求(所属したい、仲間がほしい)
- 成長欲求(Growth)
文字通り成長し自分が望むことを成し遂げたいと欲すること。欲求階層説でいう下記に該当- 尊厳欲求(認められたい、評価されたい)
- 自己実現欲求(自分らしくありたい、成長したい)←内発的が中心に相当するものである。
ERG理論は低次欲求を満たしてなくても高次な欲求が活性化することがあります。 基本的には、生存欲求→関係欲求→成長欲求の順になりますが満たされない場合は同次・低次の欲求をより満たそうとする。
この3つの欲求を満たす為に「外発的動機付け」と「内発的動機付け」のどちらかが該当して、動機づけされて、モチベーションが高くなるという流れになります。
参考:Alderfer, C.P.(1972), Existance ,relation, and growth: Human
needs in organizational settings, Free Pless.
望んでいなければモチベーションは低下してしまう
“生存欲求”、“関係欲求”は充足されない場合には不快感を感じるが,充足された場合にはそうした欲求は行動へと動機づける力を失なうとも言われています。
ですので自身が今の状態に対して改善したいと考えていない、もしくは生活に困っていないといった、現状のままでよしと考えてしまうと欲求が低下してしまい、残りの成長欲求も今の状態でこれ以上の成長を望んでいなければ欲求が低下してしまうと言えます。
つまり欲求という何かを望んでいなければ動機づけが行われない。結果としてモチベーションは低下してしまうということになると考えられます。
③仕事は基本的に「やらなければいけないこと」だから
仕事は「やらなければいけない」と考えることで上記で言うところの動機付けになります。ですが欲求としては最低限の考えでモチベーションとしては低くなると考えられます。
岡田涼 (2006)の研究によると自己決定理論と呼ばれる上記の「外発的動機付け」と「内発的動機付け」に対して更に踏み込んだ区分を設けて4つの動機づけスタイルに分類、そのスタイルによって課題に対する興味が変化すると言われています。
自己決定理論(Self-determination theory: SDT)とは、アメリカの心理学者であるエドワード・デシ氏とリチャード・ライアン氏によって提唱された心理学理論です。簡単に言うと上記の“3つの欲求”を更に「外発的動機付け」と「内発的動機付け」が分かりやすくなるように分類したものになります。
そしてこの興味は一般的に欲求の一歩手前を意味しますので興味があれば欲求に繋がると考えられるため、どのスタイルが一番興味が高くなる、あるいは低くなる傾向になるか分かれば、モチベーションが高い、低い傾向のスタイルが分かると考えられます。
実験結果が下記になります。※私が付け加えてリスト化しています。
スタイルと因子の関係
| スタイル | 動機因子 | 興味得点 | 不安・強制感 |
|---|---|---|---|
| 高動機づけ | 同一化+内発+取り入れ | 高い(1位) | 高い |
| 自律 | 同一化+内発 | やや高い(2位) | 低い |
| 低動機づけ | すべて低い | 普通(3位) | 低い |
| 取り入れ | 取り入れ+外的 | 低い(4位) | 高い |
因子(動機の種類)
| 動機の種類 | 具体例 | 自発性 |
|---|---|---|
| 内発:内発的動機付け | ・好奇心が満たされるから ・楽しいからやる | ◎高い |
| 同一化:同一化的動機付け | ・価値があるからやる ・将来の成功に結び付くから →内発に高い負荷量 | ○やや高い |
| 外的:外的動機付け | ・褒められるからやる ・まわりからやれと言われているから →取り入れに高い負荷量 | △低い |
| 取り入れ:強制的動機付け | ・怒られるからやる ・しておかないと不安だから (○○べき、○○なければならない) | ×低い |
岡田涼 (2006)いわく、取り入れスタイルは高動機づけスタイルよりも課題に対する事後の興味得点が低くなっていた。また高動機づけ、取り入れスタイルはともに低動機づけスタイルよりも不安・強制感が高かった、という結果になっています。
引用:岡田涼, & 中谷素之. (2006). 動機づけスタイルが課題への興味に及ぼす影響 自己決定理論の枠組みから. 教育心理学研究, 54(1), 1-11.
https://doi.org/10.5926/jjep1953.54.1_1
「やらなければいけない」
ですので、仕事は「やらなければいけない」と考えることで“取り入れ”因子や“外的”因子が強く、スタイルとしては“取り入れ”スタイル(興味得点4位)になる可能性が高いと考えられます。
つまり“興味”が低く、“不安・強制感”が高いという状態になっていると言えますのでこの状態ではモチベーションは低くなる可能性が高いと考えられます。
④仕事内容や環境が合っていない
①~③の内容を考慮して下記環境の場合はモチベーションが上がらない可能性が高くなると考えられます。
| 問題の内容 | 脳・神経系の反応 | やる気への影響 |
|---|---|---|
| 成果が評価されない・偏った評価 | ドーパミン分泌が減少 | 頑張りが報われず、やる気が出にくくなる |
| 人間関係が悪い(上司・同僚との不和) | ノルアドレナリン過剰 → 警戒・疲弊状態 | ストレスが慢性化し、集中力や意欲が低下する |
| 単調な仕事で意味を感じられない | 報酬系が刺激されない | やりがいや成長を感じられず、無気力になる |
| 目標が不明確・指示があいまい | 報酬の予測ができない | 先が見えず、モチベーションが湧きづらい |
| ミスに対して過度に厳しい | ノルアドレナリン過剰 → 警戒・疲弊 | 安心できず、失敗を恐れて行動が止まる |
| 休憩・リフレッシュの時間がない | 脳が疲弊し、報酬系回路も鈍化 | 回復できず、やる気が続かない |
| 意見を言えない・心理的安全性がない | 自己表現が制限され、内発的動機が低下 | 「自分の価値」を感じられず、関与度が下がる |
| 給料や待遇が不公平・不透明 | 外的報酬への不満が内発的モチベーションにも悪影響を与える | 不満が積もり、意欲や忠誠心が低下する |
💡 補足メッセージ:
こういった環境にいると、脳内のドーパミン・ノルアドレナリン回路がうまく回らなくなり、やる気を出すにも「燃料が入らない」ような状態になります。
⑤そもそも「やる気」は行動の結果であり、最初からあるものではない
多くの人が「やる気が出ないから行動できない」と感じていますが、実際は逆です。
やる気とは、何かしらの行動を起こした“あと”に、脳内で生まれる現象と考えられます。
🧠 理由①:ドーパミンは「行動した結果」によって分泌される
ドーパミンは「報酬系」の神経伝達物質です。
→「やったら得する」「達成したら嬉しい」という期待感・快感を生みだす、ですので報酬予測や、目標達成に近づいたときに出る物質と言われています。
つまり、最初から「湧いてくる」わけではありません。
行動を起こし、ちょっとでも達成感や前進感を得られたときに、脳は「これは良いことだ」と判断し、ドーパミンを分泌する仕組みになっていると考えられています。
もちろん最初から「行動した結果の成功」を認識していれば自ずと脳が行動した結果良いことがあると判断してやる気が出るようになると言われています。
枝川義邦, & 渡邉丈夫. (2010). 行動・学習・疾患の神経基盤とドパミンの役割 (Doctoral dissertation, Waseda University).
https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/27235/files/KotoKenkyujoKiyo_2_Edagawa.pdf
具体例:「仕事のやる気が出ないときの実際のケース」
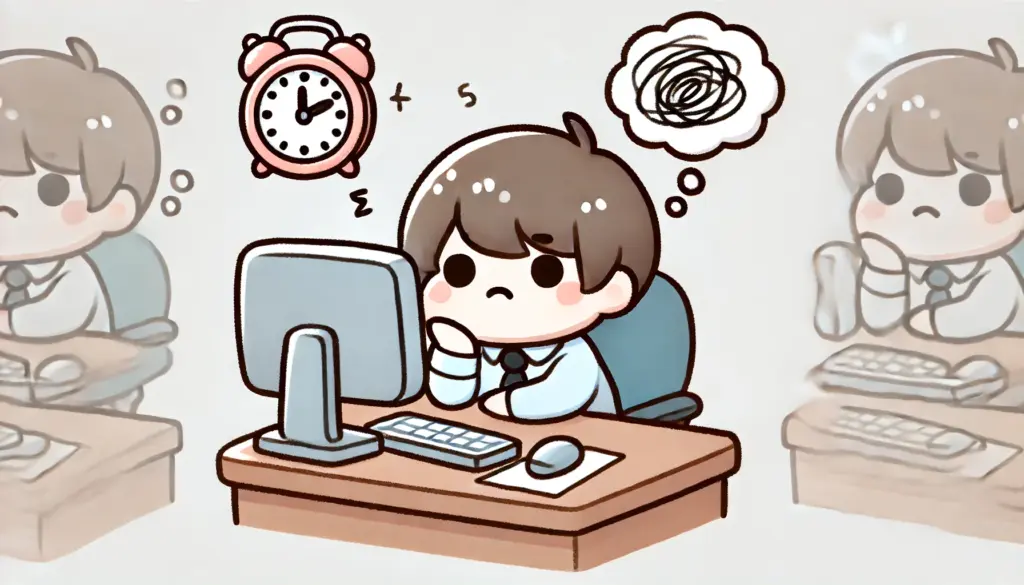
ケース1:朝から仕事に行く気がしない
対策案:
- 「やる気が出ないのは当たり前」と認める
- まずは「小さな行動」をする
ケース2:仕事が単調すぎてモチベーションが上がらない
対策案:
- 仕事の中に楽しみや工夫を加える
ケース3:人間関係のストレスでやる気がなくなる
対策案:
- 仕事の目的を見直す
対策案:「やる気がなくても仕事を進めるための方法」
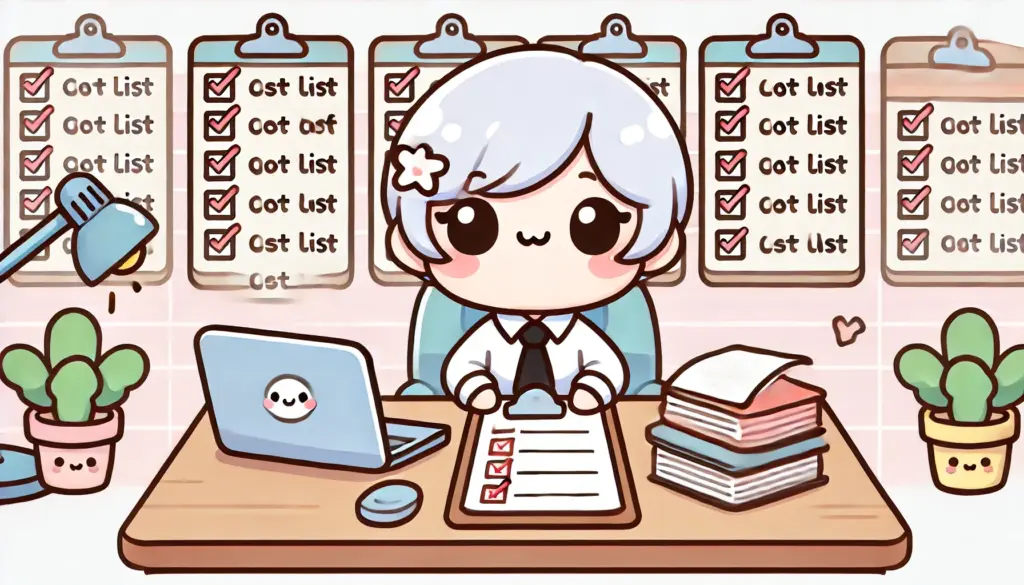
① 「やる気が出ないのは当たり前」と認める
私たち人間のモチベーションの仕組みがわかったことで普段から「やる気が出ないのは当たり前」だったんだな、ということを素直に認めて受け入れることで自己受容と呼ばれる“ありのままの自己を受け容れること”ができ、気持ちが楽になると考えられています。
- 自分の気持ちを否定せずに受け入れることで、無理にやる気を上げようとするストレスが軽減される。
- 「やる気がないからダメ」と思わず、無理にモチベーションを上げようとしない。
- 人間は常にモチベーションを維持できるわけではない。
- 大事なのは「やる気を出す方法」を知ることや、「やる気がない状態とどう向き合うか」を考えること。
私の体験談
私はやる気がないのが本当に苦痛で仕方が無かったです。なんで自分はこんなにやる気ないんだろうって責めていましたし、人生今後どうするんだろうとか悩んでいました。ですがまずは人間そんなやる気出ないものなんだなと受け入れ認めることで、気持ちが楽になりました。そこからは徐々にですがやる気が無くても大丈夫な仕組み作りとしてまずは小さな行動が簡単に出来るように考えはじめました。
② まずは「小さな行動」をする
作業を始めてから約4分ほどで作業興奮が起こり脳内ホルモンが分泌されることでやる気が高まっていく脳の仕組みでズーニンの法則と言われています。アメリカの心理学者のレナード・ズーニン博士が提唱した法則で、「最初の4分間だけ頑張ると、その後も続けてやる気が維持される」というものです。
脳の「側坐核(そくざかく)」という部分が刺激され、ドーパミンが分泌され、意欲が高まると言われています。
- 「とりあえず5分だけやる」と決めると、自然とエンジンがかかる。
- 「そもそもやる気は行動の結果で生まれる」という考え方が大切。
- タイマーを使って1分だけやってみる
- 机の上を整えるなどの簡単な準備だけやってみる
- 好きな飲み物を飲みながら、「やらないけど見てみる」くらいのゆるさで始める
- 「今日はこれだけでOK」とハードルを下げてから着手
- 体を軽く動かす(ストレッチ、深呼吸、散歩)→脳の活性化に◎
私の体験談
私はこれを知ってから何でもかんでも「とりあえず5分」と始めるクセがついてきました。そしてそれをタイマーセットします。特に筋トレとデスクワークですね。筋トレの話で、普段自宅で行っているのですがやっぱりさぼりたくなる時があります。ですがとりあえずタイマのスイッチを押す行動だけします。するとあら不思議、とりあえずやろう、まだやろう、もうちょっとやろうと逆にやめなくなります。私の中で筋肉の疲労感=結果=やった効果があるという報酬に結びついているんでしょうか、次の日筋肉痛があると嬉しいんですね。これが私の報酬の一つですから。
③ 仕事の中に楽しみや工夫を加える
笑いや楽しみがあることで仕事でもそれが「報酬」となります。そしてその「報酬」を求めてドーパミンが分泌されるようになりますので自然と動機付けができてやる気が起こると考えられます。
- 単調な仕事でも「ゲーム感覚」で進めると飽きにくい。
- やる気がなくても行動を起こせる仕組みを作る(ToDoリスト、小さな目標・ルーチン化、報酬設定など)。
- 「やる気がないと仕事ができない」とやる気を「待つ」のではなく、うまく付き合う方法を見つける。
- 「仕事は工夫次第で楽しくできる」という考え方が大切。
- 笑いを取り入れることでドーパミンの分泌を促すことに繋がる
私の体験談
自分の好きなことに関連して考えると自然とやる気が出てくるようになります。私は昔工場のライン作業をやっていたのですが、そこでも自分の中で勝手にタイムアタックしていたりして楽しんでいました。結果を1時間で○○個生産できた、という目に見える形で表されていたのも今思えば効果的だったのでしょう。
④ 仕事の目的を見直す
人が最初に動くきっかけは外的報酬の場合が多く、仕事も多くの方がお金の為に仕方がないから働いていると考えていると思います。ですが最初はお金の為だったり、誰かに指示されて流されてやっていたことでも、自分なりの意味を持つことができるようになり、そして徐々に興味を持つようになり、自分から進んで物事に取り組めるようになると言われています。
つまりきっかけは外的動機づけ(外的報酬)であっても、途中から興味を持って、価値を見出す、好奇心が生まれる、楽しくなる、など内的動機づけ(内的報酬)に変化する可能性があるということです。
その為にも何も考えずに働くより下記を意識して働くことで興味が持てるようになるかもしれません。
- 「なぜこの仕事をするのか?」を考え直すと、やる気のスイッチが入ることも。
- お金のためだけでなく、「成長」「経験」といった別の視点を持つとモチベーションが変わる。
- 目的の為にと仕事の人間関係は割り切って考える
⑤ 生活習慣を整える(睡眠・食事・運動)
モチベーションはドーパミンといった脳内のホルモンが関係していると解説しましたが、これはつまり精神論ではなく、脳内で分泌しているホルモン、つまり物理的なものが影響しているということと考えられます。
そして各ホルモンの分泌には睡眠・食事・運動といった生活習慣が影響してくると一般的に言われていますので下記を意識して生活習慣を整えることが大切と考えられます。
| 脳内物質 | 主な働き | 分泌を促す健康習慣 |
|---|---|---|
| ドーパミン | やる気・快感・達成感の源。モチベーション向上 | – 運動(特に有酸素運動) – 小さな目標達成 – 瞑想・感謝習慣 – タンパク質(チロシン)摂取。(チーズ、バナナ、納豆、豆腐、ナッツ) – ビタミンB6 |
| ノルアドレナリン | 集中力・判断力・ストレス対応。覚醒と緊張感を高める | – 朝の日光浴 – リズム運動(ウォーキング・ストレッチ) – 良質な睡眠 – 冷水シャワーや軽い刺激 |
| エンドルフィン | 鎮痛・幸福感・安心感をもたらす。自然の鎮痛剤 | – 笑う・泣く – 軽めの運動やストレッチ – 音楽やアートに触れる – 人との触れ合い(マッサージ・スキンシップ) |
私の体験談
私は朝食にバナナや納豆、間食にナッツを食べる、運動は週2回程度軽いものを取り入れ、笑う時は笑う、映画を見て悲しい時は素直に泣くなど習慣化して身体的な面ではホルモン分泌に問題がないだろうと勝手に思っています。(笑)
体験談

記事を書いた本人
私の仕事は一人で多くの業務をこなす必要があり、その量を見たらやる気は無くなり、それでも一応手はつけるのですがだらだら業務をこなして効率もどんどん落ちていき残業が増えて翌日の朝は疲労感が抜けないという負のスパイラル状態でした。
その為、休日でも体力回復の為とだらだら過ごすことが多く、やりたいことがあってもめんどくさい、やる気が出ないといった日々を過ごしていました。
また私に発言力が無い為にネガティブな発言をされることもあり言い返すこともできずストレスを溜める日々でした。
そしてそんな状態では上司からは「自分の意見が無いやつ」と見られて評価も上がらない悪循環に陥っていました。
ですが今回の記事の内容を実践することで「やる気がない状態とどう向き合うか」「とりあえず5分だけやる」「なぜこの仕事をするのか?」など知ることでそもそもの考え方が変わりました。
まず私の場合はとりあえず手を付けてはいましたが、それでもやる気は出てなかったと思っていたのですがこれは正確には「そこから手を止めずに業務を長時間一応こなしてはいた」ので、ある程度のやる気は出ていたと考えられます。問題はいつまでも「やる気が出ない出ないと考えていた自分の考え」が、ストレスとなり業務効率を下げていたのです。
またなぜこの仕事をするのか?と目標も無かったのでますますやる気は出ないということも分かり、「仕事は工夫次第で楽しくできる」と考えてもっと「効率よくできるか試す」など業務に変化を加え、自分の中で都度「目標」を作ったり、今後の「成長」として考えるようになりました。
そしていつしか残業があっても業務は私が疲れる前に終わり、さらに効率が上がってきたおかげで残業自体も徐々に減るようになっていきました。
結果として休日でも体力が残っており、気になっていたお店に行くなどのやりたいことができるようになりました。まためんどくさい、やる気がないと考えた時でも次の瞬間には「とりあえず5分だけやる」と考える思考回路になったようで、朝の早起きや筋トレなども継続して行うことが出来るようになり日々の生活での満足感が圧倒的に増えるようになりました。
やる気が無いからと言い訳をして行動せずにいると、更にそんな自分にストレスを感じてしまいます。そうではなくやる気が無い状態を当たり前と受け入れることで、平常時で出来るように工夫するなど改善意欲が湧き、いつの間にかやる気が出てたりもします。
そうでなくてもやる気が無い平常時で仕事が楽にこなせるようになれば、後は休日に楽しみを増やして行くなど活動することで日々の生活は楽しくなっていくことでしょう。
📝【まとめ】ストレスを溜めない状態を作ろう
重要なポイントとしては下記になります。
- やる気の波は誰にでもある
- やる気がなくても仕事はできる
- 「やる気が出ない=自分がダメ」ではない
- どうやって付き合うかが重要
- 「やる気が出ないのは当たり前」と認める
→ありのままの自己を受け容れること”ができ、「やる気がない状態とどう向き合うか」を考えること。 - まずは「小さな行動」をする
→ 「とりあえず5分だけやる」と決めると、自然とエンジンがかかる。 - 仕事の中に楽しみや工夫を加える
→ 「仕事は工夫次第で楽しくできる」という考え方が大切。 - 仕事の目的を見直す
→ 最初に動くきっかけは外的報酬でも視点を変えれば内的報酬に変わる - 生活習慣を整える(睡眠・食事・運動)
→ やる気は脳のエネルギー状態に影響される。
🌱 最後に:あなたに伝えたいこと
「やる気がないのは普通のこと。それでも前に進む方法はいくらでもある!」
今回の記事を読んで頂くことで、「やる気がないことに悩むのではなく、どうやってうまく付き合うか」を考えられるようになれば幸いです!
あなたがこの記事を読んで、自分のやりたいことや幸せに目を向けられる生活をする手助けになっていれば嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 楠奥繁則 (2004)。 職場におけるストレス・マネジメントの探究.立命館経営学, 42 (6), 115-133.
- Alderfer, C.P.(1972), Existance ,relation, and growth: Humanneeds in organizational settings, Free Pless.
- 岡田涼, & 中谷素之. (2006). 動機づけスタイルが課題への興味に及ぼす影響 自己決定理論の枠組みから. 教育心理学研究, 54(1), 1-11.
- 枝川義邦, & 渡邉丈夫. (2010). 行動・学習・疾患の神経基盤とドパミンの役割 (Doctoral dissertation, Waseda University).
- 下光輝一. (1993). 超持久運動後における血漿 β エンドルフィン濃度の変化と感情・気分との関係. 東京医科大学雑誌, 51(2), 116-124.