仕事でやりたいこと、今の仕事でよいのかと考えがちなあなたへ
「やりたい仕事が分からない」
「どの仕事が向いているのか分からない」
「将来の仕事の選び方に迷っている」
「親や周囲の期待に振り回されて、自分が何をしたいのか分からない」
「何をすればいいか分からず行動できない」
「やりたい仕事が分からない」と悩む人は少なくありません。しかし、未来は予測不可能であり、今存在しない職業が数年後には主流になることもあります。そんな中で、何を基準に仕事を選べばいいのでしょうか?
その答えの一つが「価値観を軸にすること」です。「何をしたいか」ではなく、「何を大切にしたいか」を考えることで、変化の多い時代でもブレないキャリア設計ができると考えます。
やりたい仕事が分からないと悩んでいる人が、価値観を軸にして自分に合った働き方を見つける方法を解説します。
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、今までの経験の1つとして転職を5回以上しております。ですが満足する結果に繋がらない、自分でも何が駄目なのか分からず右往左往していました。
ですが記事にある対策の1つ「現在の仕事や環境が価値観と合っているか確認する」ことでなぜ自分が今の現状に不満を感じているのかが理解でき、他にも「1年後の自分に向けた手紙を書く(目標を立てる)」などの対策を実施することで、少しずつ変化を加えて、結果として30代後半で再度転職をしました。
この記事では、「仕事で何がしたいか分からない」と悩んでいる読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
🔍【結論】仕事を選ぶには価値観を明確にし、変化に適応する考え方が必要
「何をしたいか」が分からなくても、「どんな働き方がしたいか」「何を大切にしたいか」が分かれば、進むべき道が見えてきます。スキルや環境よりも、「価値観」を軸に仕事を選ぶことが、長期的な満足につながるのです。
🧠【なぜ?】仕事で何がしたいか分からないと悩む原因

(1) 未来を予測しようとしすぎる
「将来性のある仕事を選びたい」と思っても、未来の業界動向を正確に読むことは不可能です。それよりも、自分がどんな価値観を持っているかを明確にし、それに合った仕事を選ぶ方が現実的だと考えられます。
体験談
私はまずこの問題で、考えても分からない不確定な未来のことばかり考えてしまい、結果として分からないからいつまでも悩むというループに陥ってしまいました。ですが分かること、つまり自分が何が大切かという価値観に目を向けることで、どのように進む方が自分にとって良いか分かるようになりました。
(2) 他人の価値観に左右される
親や周囲の期待、社会的評価に引っ張られて仕事を選ぶと、本当に自分が満足できる働き方にはならないことがあります。「自分にとって何が大切か?」を軸に仕事を考えることがやりがいに繋がると考えられます。
体験談
私は将来の夢もなければ自分の軸というものをあまり持っていなかったため、当時は周りの友人に合わせるように似たような職種を選んでいました。ですが上記にある価値観を見直すことで少しずつですが、自分の進みたい方向が見えてくるようになりました。
(3) 「やりたいこと探し」にこだわりすぎる
「やりたいことが分からない」と悩むよりも、「どんな働き方が合っているのか?」を考える方が解決策に近づきます。仕事は一つに固定せず、変化し続けるものと捉えることで働き方の方向性は見失わずに進んでいけると考えられます。
体験談
私はやりたいことを見つけなきゃいけない、そうしないと自分らしく生きられない、自分の軸がない人間になってしまう。そんな風に考えていました。ですがそもそもやりたいことが見つからないといけないわけではないと気づきました。やりたいことというのは変化しないものではないので、今やりたいことが無くても将来出来る可能性がある。で、あればあくまでも価値観は指標として、自分にとって合っている働き方を見つけることが臨機応変に対応できる方法であると気付いたのです。もちろん価値観から信念といえるほどのやりたいことが見つかればそれにこしたことはありませんが、今見つからなければ進んで行った先で見つかるものかもしれません。
💡ワーク・エンゲイジメントが重要
ワーク・エンゲイジメントとは仕事にポジティブな感情を持ち、充実している状態を指します。仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態ともいえます。
島津明人. (2010)によると、このワーク・エンゲイジメントが高い人は心理的苦痛や身体愁訴が少ないことが明らかにされているとあります。
つまりこのワークエンゲイジメントを高めることができればやりたいことでなくとも充実していると言えます。
3つの要素
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 活力(Vigor) | 精力的に仕事に取り組めるか |
| 熱意(Dedication) | 意義や価値を感じながら仕事に関われるか |
| 没頭(Absorption) | 集中して時間を忘れるほど仕事に没頭できるか |
参考:島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.
https://doi.org/10.5058/stresskagakukenkyu.25.1
💡【対策案】仕事でやりたいことを見つける対策5選
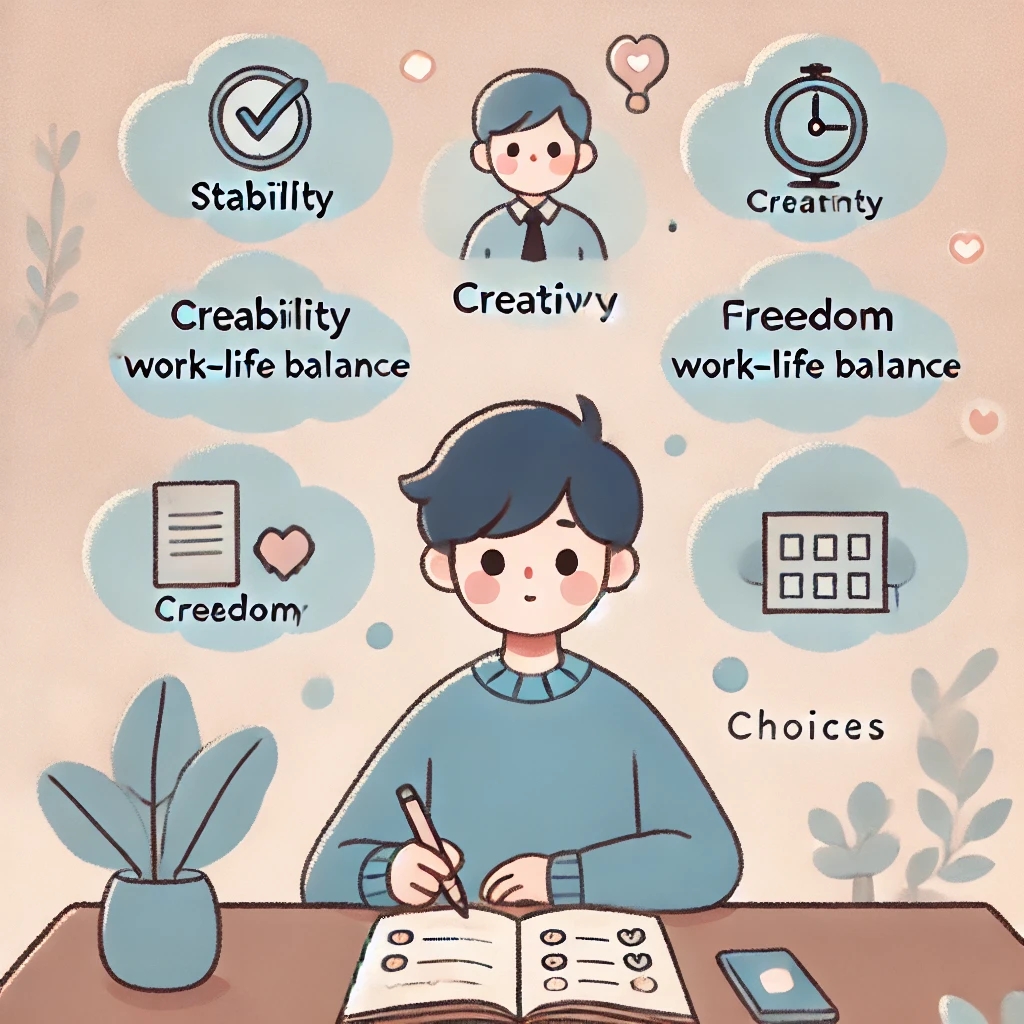
(1) 「価値観リスト」を作る
価値観は変化していくものですが、「今」の自分が大切にしたい価値観を知ることはモチベーションにも繋がるのでとても大切です。リストアップし、優先順位をつけてみるとよいと考えます。
- 例:「自由を大切にしたい」→リモートワークやフリーランスが合うかも?
- 例:「安定を重視したい」→転職より社内キャリアアップを狙う
体験談
今の社会情勢では転職というのも割と当たり前になってきました。就職時に失敗したくないという思いがあったり逆にここで終身雇用というわけではないと考えたりと、人それぞれですが、この価値観というのは自分の指標になりますので、知ることは大切と思います。
ただ、記事を書いている現在約40歳の私ですが経験や年齢を重ねることで価値観は変化していると実感できます。ですのでここで完璧に自分を知ろう!と時間をかけすぎる必要はさほどないかなとは思います。
(2) 「変化に適応する働き方」
職業や業界は時代とともに変わりますが、自分に合う働き方を探し続けることで、変化にも対応できると考えます。
- 例:数年前にはなかった仕事(動画編集者、AI関連職)が今では人気職種
- 未来の仕事は予測できなくても、「自分に合う環境を探す力」があれば適応できる
体験談
私は昔エクセルの関数など頑張って調べて活用していたりしたのですが、今ではAIでさくさくっと作ってしまうことが出来てしまいます。ただ私は自分で0から1を作るよりあるものを活用して1から10もしくは10を維持するといった働き方が合っています。それが分かっているのでAIも純粋に便利な道具が増えたといった感じで受け入れることができています。話の規模は小さいですが変化に対応することで自分の仕事に活用することもできます。
(3) 「仕事は試行錯誤で見つける」
最初から理想の仕事を見つけるのは難しいですが、実際に行動しながら自分に合う仕事を探すことが大切と考えます。
- 例:最初は事務職→マーケティング職へ転向→さらに独立
- 「この仕事が正解か?」ではなく、「この仕事で何を学べるか?」が重要
体験談
私は理想の仕事がまだ見つかってはいません。ですがそうでなくとも日々何を学べるかと考え行動していることで理想に近づいているという感覚はありますし、それで充実感を得ることもできています。理想の仕事でなくとも焦らず進んで行こうと考えることができています。
(4) 「ワーク・エンゲイジメントが高まった経験」
以下のような観点で過去を振り返ってみると、自分がどんな状況で充実感を感じやすいかが見えてきます。
- 時間を忘れて取り組んだことは?
- 自分の価値観や信念と一致していた仕事は?
- 役に立っていると実感できた瞬間は?
体験談
私は“機械保全士”という職業で機械の修理をしていた経験があります。そこでの私にとっての充実感は故障の原因に繋がる可能性を一つ一つしらみつぶしに行い、原因特定に至った時など、自分の力、もしくはチームの力でやりきってやったぞ!といった気持ちになり、とても充実していたのだと、振り返ってみて思いました。振り返らなかったら私はこの気持ちが当たり前のものと見過ごしていたかもしれません。
(5) 「ワーク・エンゲイジメントを高める」
今の職場もしくは就職先での活動となりますが、「ワーク・エンゲイジメントを高める」ことでやりたいことでなくとも充実していると言えます。
まだ改善の余地があるのでしたらワーク・エンゲイジメントを高める方法を取ることで環境を変えずに充実した仕事を得られる可能性があると考えられます。
一覧
| 要素 | 説明 | 高めるための具体的な方法 |
|---|---|---|
| 活力(Vigor) | エネルギーを持って仕事に取り組める状態 | ・適度な運動や睡眠、食事の管理 ・仕事の合間にリフレッシュタイム ・小さな目標で達成感を得る |
| 熱意(Dedication) | 意義や価値を感じて熱中できる状態 | ・仕事の「目的」や「誰の役に立っているか」を意識する ・自分の強みや得意を活かせるタスクを選ぶ ・チーム内で感謝を伝え合う文化をつくる |
| 没頭(Absorption) | 集中して夢中になれる状態 | ・通知を切る・静かな環境をつくる ・フローに入りやすい時間帯を知る ・難しすぎず簡単すぎないタスクに挑戦する |
体験談
私としてここでの大事なポイントは仕事の目標や、自分の強みを活かせるタスクであるという点になります。この二つは行動の動機付け(行動する意味、価値)や達成感を味わう為に必要です。私が機械の修理を行う時、目標が無い時期がありました。その時は本当に毎日ふわふわした気持ちで仕事をしていて達成感もなんもありません。ですが目標が出来てくると進む道が出来たみたいにシャキシャキ働け達成感も味わえます。目標達成して、仕事頑張ったなーと自分を褒めることもできました。
🎯【実践リスト】「今」すべきこと5ステップ

「今」すべきこと
対策案と内容は一部カブリますが、とりあえず今するべきことを下記にリスト化しました。
- 「価値観を明確にするワークをする」
→ 紙やノートに「自分が大事にしたいもの(自由・安定・挑戦・人気など)」を書き出す
→ それらの価値観をランキングし、「絶対に譲れないもの」を決める
エンゲイジメントが高まった経験なども〇 - 「現在の仕事や環境が価値観と合っているか確認する」
→ 価値観リストを見ながら、「今の職場・働き方はこれに合っているか?」をチェック
→ 合っていないなら、すぐに転職ではなく「どんな変更ができるか?」を考える - 「小さな行動を起こす(実験的に動く)」
→ 例:「転職を考えているなら、転職サイトに登録だけしてみる」
→ 例:「副業に興味があるなら、クラウドソーシングで1件だけ仕事を受けてみる」
→ 例:「環境は合っているがワークエンゲイジメントが低いなら、高める行動をとる」
→ すぐに大きな決断をせず、まずは動いてみることが重要 - 「フィードバックを得る」
→ 周囲の人に「自分の強みは何だと思う?」と聞く
→ 実際に新しいことを試したら、「楽しかったか?」「苦痛だったか?」を振り返る - 「1年後の自分に向けた手紙を書く」
→ 「理想の1年後の自分」をイメージし、それに向けて今できることを書き出す
→ 未来は予測できないが、目標は持っておくことで軌道修正しやすくなる
体験談
私はまずこれらを始めました。これらの活動を行っていくことで少しずつ自分の大切にしていること、やれること、どんな得意分野があるのか、など知ることでどんな働き方が合っているかを少しずつ知ることができました。
✍【体験談】

記事を書いた本人
私の仕事は50%ルーティンで50%臨機応変に対応するといった業務バランスで、残業がある程度ありますが土日と長期連休も取れて給与もそこそこな、バランスの良い企業。
ただ仕事をしていても達成感もあまりなく、でもじゃあ何を変えたいのかと問われると答えられない、自分のことなのに何が駄目なのか分からず悩み、不満が多い毎日を過ごしていました。
ですが記事にある対策の1つ「現在の仕事や環境が価値観と合っているか確認する」ことでなぜ自分が今の現状に不満を感じているのかが理解できました。それは今の職場では人を蔑ろにして効率をひたすら求める風潮があり、そこが自分の価値観である「他人に配慮する」という気持ちとマッチしていないということです。
ですのでどんなに条件が良くても業務を嫌々やっている感じがするのだと理解することができました。他にも多々ありますが私の中では一番はここです。他の価値観・・・「知識・平安・独立・信頼」など。
そのうえで対策の1つ「1年後の自分に向けた手紙を書く(目標を立てる)」ことで、より具体的に自分が今後どうしていきたいかをじっくり考えることができ、私の場合は1年と+αで5年10年後くらいまで「こう進めたらいいな」くらいの気持ちで「自分で会社を興す」と書きました。
その後としては最終的には30代後半で再度転職をしたわけですが、その前にいくつかの葛藤はあり、純粋に価値観にしたがって後先考えず転職をしたというわけではありません。
対策の1つ「小さな行動を起こす(実験的に動く)」として転職サイトに登録はもちろんのこと他にも現職場と転職先、他にもいくつか転職候補を別口で探し、ありとあらゆる面を表にして何度も比較し、実際に金銭的メリットや今後の目標に繋がる可能性を考慮して、最終的に転職するという結論にいたりました。
私の目標としては、自分で会社を興すという目標を立てて行動しています。ただこれは絶対に達成できなければならないというわけではありません。あくまで私の価値観に合った目標が会社の先にあるだけです。
その途中経過としての転職になりますが、それでも以前と比べ自分の価値観である「他人に配慮する」という風潮がある企業ですので気持ちよく働くことができ、また目標の会社経営に向けてより多くの経験を積むことができており、目標達成していない現在でも以前より人生が楽しく思えるようになりました。
価値観に全てが合っていなくてもより理想に近づく行動をしているだけで人は充実感を得ることができます。私は転職に特に抵抗が無いため、比較した結果として転職しましたが、転職でなくとも考え方を変えることでいくらでも手を打つことはできます。
大事なことはある程度価値観に合った、ワークエンゲイジメントが高い活動をすることになり、そうすることで日々の生活は楽しくなっていくことでしょう。
📝【まとめ】仕事は「価値観×適応力」で決まる
重要なポイントとしては下記になります。
- 「やりたいことが分からない」なら、まずは「何を大切にしたいか」を考える
- 一度選んだ仕事に固執せず、環境変化に応じて柔軟に進化することが大切
- 小さな行動を起こす。大きな決断をせずまずやれる範囲で動いてみる
- 「価値観を明確にするワークをする」
→ 自分が大事にしたいものを書き出す - 「現在の仕事や環境が価値観と合っているか確認する」
→ 「今の職場・働き方はこれに合っているか?」をチェック - 「小さな行動を起こす(実験的に動く)」
→ すぐに大きな決断をせず、まずは動いてみることが重要 - 「フィードバックを得る」
→ 実際に新しいことを試したら、「楽しかったか?」「苦痛だったか?」を振り返る - 「1年後の自分に向けた手紙を書く」
→ 未来は予測できないが、目標は持っておくことで軌道修正しやすくなる
🌱 最後に:あなたに伝えたいこと
仕事は固定されたものではなく、常に更新し続けるものです。価値観を明確にし、どんな働き方が合っているのかを考え、小さな行動を積み重ねながら、自分らしい働き方を見つけていきましょう。
今回の記事を読んで頂くことで、「どの仕事が向いているのか分からない」と悩むのではなく、「何を大切にしたいか」を考えられるようになれば幸いです!
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.
