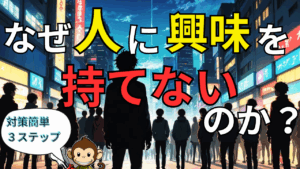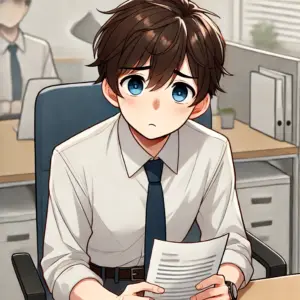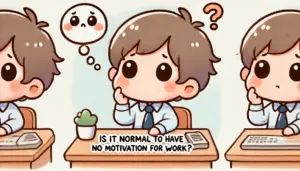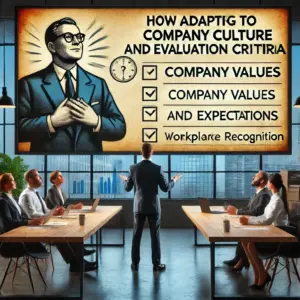職場の人間関係でストレスを溜めてしまいがちなあなたへ
「職場で評価されなくてストレス」
「上司がちゃんと評価してくれない」
「取引先からの評価がおかしい」
夜遅くまで残業して、ミスが起きないように細部まで工夫して――
それでも評価されるのは、要領のいい人や“声が大きい人”。
「自分の努力って意味あるの?」
そう思って、心が折れそうになることはありませんか?
でも、その“くやしさ”や“空しさ”にはちゃんと理由があります。
そして、そこから回復する方法も、脳の仕組みにヒントがあります。
昔の私は評価されなくても、いつかは評価される。だから残業が多くても仕事が自分に集中しても頑張らなくちゃいけない。そう考えて苦しんでいました。
そんな生きづらいと感じていた私が、人生は楽しいと考えられるようになった考え方の一つを紹介します。
- 【原因】ストレスになるのは脳にとっては「無意味な努力」になってしまうから
- 【なぜ?】評価は「真実」ではなく「その人の主観」
- 【ポイント】一番大切な評価者は「自分自身」
- 【対処】自分を認める習慣など(全4ステップ)
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして職場の人間関係で悩み苦しみ、辛かった思いをしてきました。
ですが記事にある「脳にとっては無意味な努力」という考え方から。確かに今まで他人に自分を評価してもらうことを考えていたが、その後は他の対策を実施することで、現在は昔であればストレスだったであろう事も全くストレスと感じなくなり、以前より人生が楽しく思えるようになることができました。
この記事では、「理不尽な思いでストレス」を感じる読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
結論「自分の評価が大切」
私たちが評価されず苦しいのは「脳の報酬系」が働かないからで、これはごくごく自然な反応と言えます。
そしてその評価を他人に委ねてしまうことは自分のエネルギーを他人に左右される不安定な状態になってしまいます。
大切なのは、評価してもらうことではなく、自分自身で評価することになります。
🧠【なぜ?】「評価されないとつらいのか」

仕事の報酬
私たちの脳には「報酬系」と呼ばれるシステムがあります。
努力や達成を感じたときに、ドーパミンという快楽ホルモンが分泌され、
「やってよかった」「また頑張ろう」と感じるわけです。
でも、外からの評価がないと、この報酬系がうまく働かなくなります。
つまり――
がんばっても認められない=脳にとっては「無意味な努力」になってしまう
このとき、脳は「もうやめよう」「頑張ってもムダだ」と学習してしまいます。
でもこれは「あなたの心が弱い」わけではなく、脳の自然な反応と言えます。
参考:筒井健一郎, & 渡邊正孝. (2008). 報酬の脳内表現. 生理心理学と精神生理学, 26(1), 5-16.
https://doi.org/10.5674/jjppp1983.26.5
枝川義邦, & 渡邉丈夫. (2010). 行動・学習・疾患の神経基盤とドパミンの役割 (Doctoral dissertation, Waseda University).
https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/27235/files/KotoKenkyujoKiyo_2_Edagawa.pdf
ワーク・エンゲイジメントが低下する
ワーク・エンゲイジメントとは仕事にポジティブな感情を持ち、充実している状態を指します。仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態ともいえます。
島津明人. (2010)によると、このワーク・エンゲイジメントが高い人は心理的苦痛や身体愁訴が少ないことが明らかにされているとあります。
ワーク・エンゲイジメントが高い人の条件に社会的な要因として、“目標の達成や促進、個人の成長”などがあります。
目標として何も設定していない人でも自分でも気づかないうちに自然と上司からの評価を目標にしている人は多いと思います。
ですが評価を得られないということは、この目標が達成できない、自分の努力が認められないと感じてしまうことに繋がり、ワーク・エンゲイジメントが低下してしまいます。
参考:島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.
https://doi.org/10.5058/stresskagakukenkyu.25.1
自尊心が低下してしまう
自尊心とは「ありのままの自分を受け止めることができる感覚」や「プライド」など様々な言われ方があるが、このサイトでは「自分の存在価値を認めること」としており、自己肯定感とほぼ同じです。
大きな違いとして自尊心は自分の能力や成果で評価する、それが高いかどうかは他者からの評価を基に感じる傾向が高い為、他者の影響を受けやすい。多くの場合幼少期~青年期に至るまでに多くが決定付けられているとされます。
自己肯定感は自分の現状をありのまま受け止める為、能力が無くても問題ないと考える。
簡単に言うと「他者のまなざし」に左右されるかどうかの違いで、評価されなくてつらいと考える場合、この自尊心が低下している可能性があります。
参考:井上信子. (1986). 児童の自尊心と失敗課題の対処との関連. 教育心理学研究, 34(1), 10-19.
https://doi.org/10.5926/jjep1953.34.1_10
仕事の成果が正しく評価されない
心理的要因: 江本リナ. (2000)によると「自己効力感」と呼ばれる自分が持っている能力に対する自信や確信が下がると、不安や恐怖が強く表れる傾向にあるとされています。
簡単に言うと、モチベーションや行動力にブレーキがかかってしまい、次第に“無力感”や“諦め”が当たり前といった状況を生み出してしまうと考えられます。
この自己効力感は自身の能力に対する自分の評価ですので、それは他人からの評価でなくても良く、仕事の成果ではなく、自分はこれがやれると確信していることで自己効力感を上げることができると考えられます。
江本リナ. (2000). 自己効力感の概念分析. 日本看護科学会誌, 20(2), 39-45.
https://doi.org/10.5630/jans1981.20.2_39
🏭 脳内保全士の視点で見る「評価されないときの脳内工場」
脳を工場にたとえてみましょう。
- 通常時の流れ
努力投入 (=エネルギー)→工場ライン稼働 → 出荷評価(=出力) → 報酬としてドーパミン分泌 - トラブル発生時
がんばっても評価されない=「出荷場の故障」
→ 報酬が出ず、それでもラインを稼働して、ラインが過剰運転に。 - 予兆サイン
→ 過剰運転の結果、無理がたたってラインが故障。
思考としては「もうどうでもいい」「何のために働いてるんだろう」といった状態に。
 ひろのぶ
ひろのぶかつての自分は報酬という評価がいつか貰えると思って、無理に頑張ってしまった結果、心も体も疲れ果てしまいました。
💡【実施】それでも折れない心を育てる4つのステップ


✅ ① 「他人の評価=不安定装置」と割り切る
上司の評価は、天気のように気まぐれなこともあります。
体調・機嫌・先入観――すべてが影響します。
大事なことは評価は「真実」ではなく「その人の主観」。
主観という不安定な装置に自分の感情が左右される状況だったのだと、
そう認識するだけで、私たちの脳の機能、扁桃体(怒り・不安の感情を生む部位)の過剰反応は落ち着いていきます。
扁桃体は、脅威を感じたときやストレスを感じたときに活発になる場所です。評価が自分に対してネガティブだと感じると、扁桃体が反応し、怒りや不安などの感情が強くなると考えられています。
参考:田積徹. (2013). 恐怖の古典的条件づけと扁桃体: LeDoux モデルの再考と今後の展望. 人間科学研究, 34, 73-84.
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/2272
✅ ② 内的報酬を育てる
外からの評価が得られないなら、自分の内側に報酬を作りましょう。
たとえば――
- どんな工夫をした?
- 自己記録をつける(自分だけの成果メモ)→内的な報酬を感じる回路を育てる。
- 何に時間をかけた?
- 評価されない前提で「学習」として仕事を捉えると、自分の中での意義が生まれやすい。
- 昨日より良くなった点は?
- 小さな成功や努力を言語化して、自己承認の回路を育てる(扁桃体の“価値判断”を良い方向に修正)。
こうして自分で認める習慣を作ることで、脳の機能、前頭前野(理性・自己評価をつかさどる部位)が
「確かに頑張った」と判断し、ドーパミンが分泌されやすくなります。
参考:増尾好則、東邦大学、ストレスと脳、2025/4/3
https://www.toho-u.ac.jp/sci/bio/column/029758.html
✅ ③ 比較の矢印を「他人→過去の自分」に変える
評価される他人と比べると、脳は「負け=危険」と認識してストレス反応が出やすくなります。
でも、昨日の自分より少し成長したという認識は、ドーパミンを自然に分泌させます。
脳が一番心地いいのは、“ちょっとした成長”です。
✅ ④ 「何のために働いているのか」を思い出す
評価されるために働いている――そんなふうに感じる日もあるかもしれません。
でも少し深掘りすると、本当の動機が見えてきます。
- スキルを身につけたい
- 家族を支えたい
- 自分の生活を安定させたい
“自分軸”を思い出せば、他人の評価に左右されすぎない強さが育ちます。
📝【まとめ】ストレスを溜めない状態を作ろう
重要なポイントとしては下記になります。
- 評価されず苦しいのは「脳の報酬系」が働かないから(=自然な反応)
- 他人評価は不安定。絶対ではなく“ただの主観”と捉えてみる
- 成果は「自分の言葉で記録」することで“内的報酬”に変えられる
- 比較は「他人」ではなく「過去の自分」とすることで脳にご褒美が出る
- 働く理由を“他人評価以外”の自分軸で思い出すと、心のブレが減る
- 自分の努力は、見えなくても“確実に積み重なっている”
- 一番大切な評価者は「自分自身」。自分を見捨てないことが何より大事
- 「他人の評価=不安定装置」と割り切る
→大事なことは評価は「真実」ではなく「その人の主観」。 - 内的報酬を育てる
→ どんな工夫をした?など自分で認める習慣を作る。 - 比較の矢印を「他人→過去の自分」に変える
→ 昨日の自分より少し成長したという認識。 - 「何のために働いているのか」を思い出す
→ 自分の生活を安定させたいなど“自分軸”を思い出せば、他人の評価に左右されすぎない
🌱 最後に:あなたに伝えたいこと
評価されないときほど、「自分は価値がないのかも」と思ってしまいがちです。
でも――
見ている人は、ちゃんといます。
同僚かもしれないし、後輩かもしれない。
あるいは「未来の自分」かもしれません。
そしてなにより大事なのは――自分が自分を認めること。
それが、外的評価よりもずっと大きな「心の防振装置」になります。
あなたがこの記事を読んで、自分のやりたいことや幸せに目を向けられる生活をする手助けになっていれば嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 筒井健一郎, & 渡邊正孝. (2008). 報酬の脳内表現. 生理心理学と精神生理学, 26(1), 5-16.
- 枝川義邦, & 渡邉丈夫. (2010). 行動・学習・疾患の神経基盤とドパミンの役割 (Doctoral dissertation, Waseda University).
- 島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.
- 井上信子. (1986). 児童の自尊心と失敗課題の対処との関連. 教育心理学研究, 34(1), 10-19.
- 田積徹. (2013). 恐怖の古典的条件づけと扁桃体: LeDoux モデルの再考と今後の展望. 人間科学研究, 34, 73-84.
- 増尾好則、東邦大学、ストレスと脳、2025/4/3