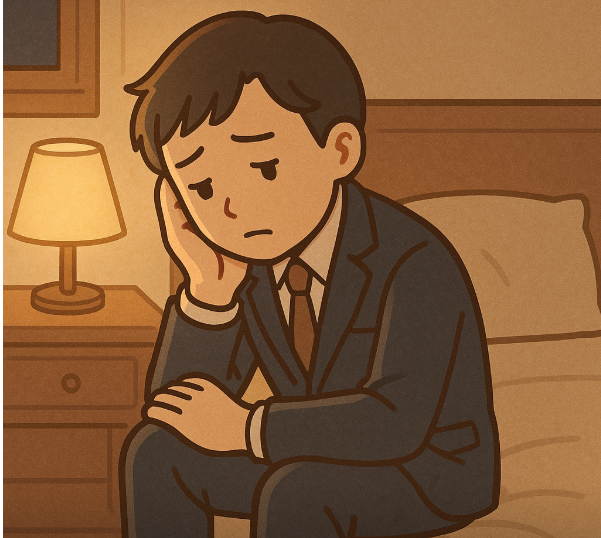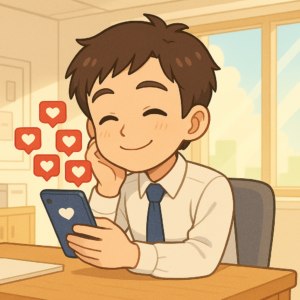つい自分を責めてしまうあなたへ
「またダメだった」 「なんで自分はこんなこともできないんだろう」
そんなふうに、自分に対して厳しい言葉をかけてしまうことはありませんか?
うまくいかない日や、失敗したとき、私たちはつい自分を責めがちです。ですが、その裏には「もっとちゃんとした自分でいたい」「認められたい」という思いが隠れています。
今回は、そんな“自分責め”から少しずつ抜け出すための考え方、「自己受容」について詳しく解説します。
- 自己受容とは、「できない自分」も含めて、自分をそのまま受け入れること
- 自己否定をやめることで、心に余裕が生まれ、前に進む力が整う
- 小さな実践ステップを通して、他人と比べず、やさしく自分と向き合う方法が学べる
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして職場の人間関係で悩み苦しみ、辛かった思いをしてきました。
この記事では、「つい自分を責めてしまう」読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
【結論】自分をまるごと認める
自己受容とは、弱さやできない部分も含めて、自分をまるごと認める力です。
他人と比べるのではなく、「今の自分」にOKを出すことが、心の回復と前進への第一歩になります。
失敗や落ち込みの中にも、受け止める力が育てば、人生はもっとやわらかくなっていきます。
自己受容に似た言葉
自己理解・自己肯定・自己承認…結局なにがどう違うの?どれが今自分に必要なの?そう思った方は関連する言葉と意味をまとめた記事がありますので良ければそちらをご覧ください。
【なぜ?】自己受容ができない理由
自己受容とは?
自己受容とは、「できない自分」「情けない自分」「感情が揺れる自分」なども含めて、「自分自身を、好ましい面も好
ましくない面も含めて受け容れること」です。
他にも自身の人間性を、すべてその欠点を認め、理想の姿とは食い違っていることを承知しながらも、受け入れることができる。
自己の長所や短所、能力やその限界・欲求などを、誇示・自己非難などの不当の感情を入れることなしに、客観的に認知すること、など様々な言われ方をしています。
これは“甘やかす”ことではなく、「今の自分を正しく見る」ことで、無理なく前に進むための土台となる力です。
なぜ自己受容が大切なのか?
自己受容は、「自分の味方でいる力」と言い換えることもできます。
- 自分を否定し続けると、やる気や自信が失われていく
- 完璧であろうとするほど、失敗が怖くなり行動できなくなる
- 自己受容があると、「たとえ失敗しても大丈夫」と思える心の余白が生まれる
 ひろのぶ
ひろのぶ私はこの言葉の意味を知る前までは、自分で自分を責める状態で、前も後ろも敵だらけとなってしまっていました。
自己受容がループする
自分が自分の味方でいること自己受容が高まり、周りにも影響があり、自分の自己受容が更に高まるといったループ状態ができると考えられています。ですが逆に言えば自己受容が出来ていないとなかなか自己受容を高めることが出来ないともとれます。
春日由美. (2015)いわく自己受容は他者受容と密接な関係を持ち、人間関係や他者からの受容とも関連することが示唆されたと言われており、簡単にまとめると下記になります。
- 自己受容は他者受容と同時に起こるか、あるいは自己受容が他者受容を促進すると考えられる。
→自分の味方でいることで、他人も味方にできる。また、促進できると考えられる。 - そしてそれが良好な人間関係の構築につながると考えられる。
→結果として人間関係が良くなることにつながる。 - 他者からの受容は自己受容を促進すると考えられるが、良好な人間関係を築くことにより、他者からの受容も得られやすくなり、それが更に自己受容を促進するといった循環が生じることが推測される。
→自分の味方でいることで周りが味方になるループができると考えられる。
参考:春日由美. (2015). 自己受容とその測定に関する一研究. 南九州大学人間発達研究, 5, 19-25.
https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDR5_0003.pdf
自己受容ができない理由とは?
下記の思考のクセが、無意識に「自己否定」を強化してしまうと考えられます。
- 完璧主義:「ちゃんとできない自分は価値がない」と思ってしまう
- 過去の否定体験:親や先生に厳しく育てられた/失敗を許されなかった経験
- 他人との比較癖:SNSや職場などで他人と比べて落ち込む
参考:春日由美. (2015). 自己受容とその測定に関する一研究. 南九州大学人間発達研究, 5, 19-25.
https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDR5_0003.pdf
【対策案】
春日由美. (2015)いわく自己受容とは、ありのままの自己を受け入れようとする自己に対する「態度」や「姿勢」、またはその「過程」を意味していると考えられたと言っており簡単にまとめると下記になります。
- 客観的に距離を置いてみることができる態度
- ただ素直に「今の自分はこうなのだ」と暖かく受け止めようとする姿勢
- 意識ではなく、感情や感覚といった過程
ですので対策案としては客観的な態度、素直に受け止める姿勢、そして自己受容は感情や感覚といった過程である。この内容を軸にした実践リストが次になります。
参考:春日由美. (2015). 自己受容とその測定に関する一研究. 南九州大学人間発達研究, 5, 19-25.
https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDR5_0003.pdf
【実践リスト】自己受容を高めるための4つのステップ
① 感情に名前をつけてみる
まずは自分の気持ちを“否定せずにそのまま見つめる”ことから。
嬉しい・悔しい・しんどい…など、湧いてきた気持ちをただ感じる
「こんな風に感じるのはダメ」と思わず、感じたままを受け止める
例:「今、悔しいと思ってるんだな」「ちょっと疲れてるだけかも」
感情のラベリングと呼ばれる手法になります。
この手法は、自分が現在感じている感情を言語化することで、情緒的な自己認識を高め、ストレスの軽減や感情の調整に役立つとされています。
- 感情のコントロール:自分の感情を言語化することで、感情に振り回されず冷静に対処できるようになります。
- 自己理解の向上:自分の感情を明確に認識することで、内面を深く理解できるようになります。
- ストレスの軽減:感情を言葉にすることで、脳の扁桃体の活動が抑制され、ストレスが軽減されることが研究で示されています。
- コミュニケーションの改善:自分の感情を正確に伝えられるようになり、他者との関係がスムーズになります。
これらの効果により、感情のラベリングは日常生活や対人関係において有益な手法とされています。
② 「今の自分はこうなのだ」と声に出して言う
行動できなかったことより、それに気づけた自分を褒めてあげる。
評価せず、“観察する”だけの言葉かけを意識する
例:「今はやる気が出ないんだな」「今日はちょっと不安定かも」
セルフトーク(自己対話)と呼ばれる手法になります。
セルフトークとは、自分自身との内的な対話を指し、思考や感情を整理し、自己理解を深める手法です。この内的対話には、ポジティブなものとネガティブなものがあります。ポジティブなセルフトークは自己肯定感を高め、モチベーションやパフォーマンスの向上につながります。一方、ネガティブなセルフトークは自己評価を下げ、不安やストレスを増加させる可能性があります。
セルフトークを効果的に活用するためには、以下の方法が有効です
- 現在のセルフトークを把握する:日常的にどのようなセルフトークを行っているかを観察し、ネガティブなパターンに気づくことが重要です。
- ネガティブなセルフトークをポジティブに変換する:例えば、「また失敗するかもしれない」という思いを「この経験から学べることがある」と前向きな表現に置き換えます。
- ポジティブなセルフトークを習慣化する:日々、自分を励ます言葉や肯定的なフレーズを意識的に使うことで、前向きな思考を強化します。
セルフトークを適切にマネジメントすることで、自己認識が向上し、感情や行動のコントロールがしやすくなります。これにより、ストレスの軽減や目標達成への意欲向上など、多くのメリットが期待できます。
③ 日記やメモに「今の感情」を書き出す
うまく言語化できなくても、自分の心をアウトプットするだけで整理されます。
毎日3〜5分、「今の気分」「その理由」「そのままの自分に言いたいこと」を書く。
そうすることで自分の内面を客観的に見つめる習慣をつけることができます。
例:「今日は気分がのらなかった。でも、そのままで過ごせた自分を褒めたい」
ジャーナリングと呼ばれる手法になります。
「ジャーナリング」とは、一定の時間内に頭に浮かんだことをそのままノートに書き出す手法です。具体的な出来事や感情を整理して書く日記とは異なり、思いついたことを自由に書き留める点が特徴です。内容がポジティブかネガティブかに関わらず、抽象的な表現でも問題ありません。
- 自己を客観的に捉えられる: 書き出した内容を振り返ることで、自身の思考や感情を冷静に見つめ直すことが可能になります。
- 悩みやストレスの原因を明確にできる: 思考や感情を言語化することで、悩みやストレスの要因を明らかにし、整理する手助けとなります。
- ストレスの緩和につながる: 内面の感情を表現することで、心の負担が軽減され、ストレスの緩和が期待できます。
- ネガティブな感情を解消できる: 頭の中で繰り返される否定的な思考を紙に書き出すことで、感情の整理が可能となります。
原田恵理子 (2011)いわくメタ認知の手がかりとなる 「気持ちのリスト」が言語化を促進し、自他の気持ちに気づいて整理した感情を制御する力につなげたと推測されると言われています。
参考:原田恵理子, & 渡辺弥生. (2011). 高校生を対象とする感情の認知に焦点をあてたソーシャルスキルトレーニングの効果. カウンセリング研究, 44(2), 81-91.
https://doi.org/10.11544/cou.44.2_81
④ 「〜でなければならない」を「〜でもいい」に変換する
→例:「頑張らなければ」→「今日は休んでもいい」
思考のクセに気づき、やわらかい言葉で置き換える練習。
リフレーミングと呼ばれる手法になります。
リフレーミングは、主に短期療法や家族療法、ナラティブセラピーなどで用いられる技法で、物事の見方や捉え方を新しい視点で再解釈することを指します。例えば、困難な状況を「大変な問題」と捉えるのではなく、「成長の機会」と見なすことで、前向きな感情や行動を促進しますと言われています。
やり方(4ステップ)
- 今の捉え方を書き出す
- 例:「ミスして上司に注意された。自分はダメだ」
- その出来事に別の意味を与えてみる
- 例:「指摘されたのは、ちゃんと見てくれている証拠かもしれない」
- ポジティブな視点に言い換える
- 例:「ミスから学べた。次はうまくやれそうだ」
- 「役に立つ視点」を選ぶ
- リフレーミングは“正しさ”よりも、“前に進めるか”が大事。
効果
- モチベーションの向上:困難な状況を成長の機会と捉え直すことで、やる気が高まります。
- 人間関係の改善:相手の言動を別の視点から理解し、コミュニケーションが円滑になります。
- ストレスの軽減:ストレスの原因となる出来事の意味付けを変えることで、感情的な負担が和らぎます。
- 課題解決能力の向上:問題を多角的に捉えることで、新たな解決策を見出しやすくなります。
このように、リフレーミングは思考の柔軟性を高め、前向きな行動を促進する効果があります。
参考:鬼塚拓、オニツカタク。 (2019年)。 リフレーミング能力を育成するための社会科学習指導の方法.宮崎大学教育学部附属教育協働開発センター研究紀要, 27 , 17-32.
https://miyazaki-u.repo.nii.ac.jp/record/5801/files/p17-p32.pdf
自己受容と他の視点の違い
| 観点 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 自己受容 | ありのままの自分を認める | 失敗・感情・弱さなど |
| 自己承認 | 自分の努力・行動を認める | 成果・行動・挑戦など |
| 自己肯定感 | 「自分には価値がある」と感じる | 自分の存在そのもの |



自己受容は「感情や状態」にOKを出す基盤。他の視点と組み合わせることで、心の回復力が高まります。
自己承認
自己承認は自己受容の次のステップみたいなもので、とても関連する内容になっていますので、もし良ければ下記記事を読んでください。
最後に:あなたに伝えたいこと
自己受容は、ダメな自分を放置することではありません。
「うまくいかない時の自分」も受け止めながら、前に進む準備を整える力です。
あなたが今、うまくいかないと感じていることも。 やる気が出なくて動けなかった日も。
そのすべてが、あなたの人生の一部であり、大切な経験です。
あなたがこの記事を読んで、自分のやりたいことや幸せに目を向けられる生活をする手助けになっていれば嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 春日由美. (2015). 自己受容とその測定に関する一研究. 南九州大学人間発達研究, 5, 19-25.
- 原田恵理子, & 渡辺弥生. (2011). 高校生を対象とする感情の認知に焦点をあてたソーシャルスキルトレーニングの効果. カウンセリング研究, 44(2), 81-91.
- 大野裕(2008),慶應義塾大学保健管理センター,認知再構成法,495