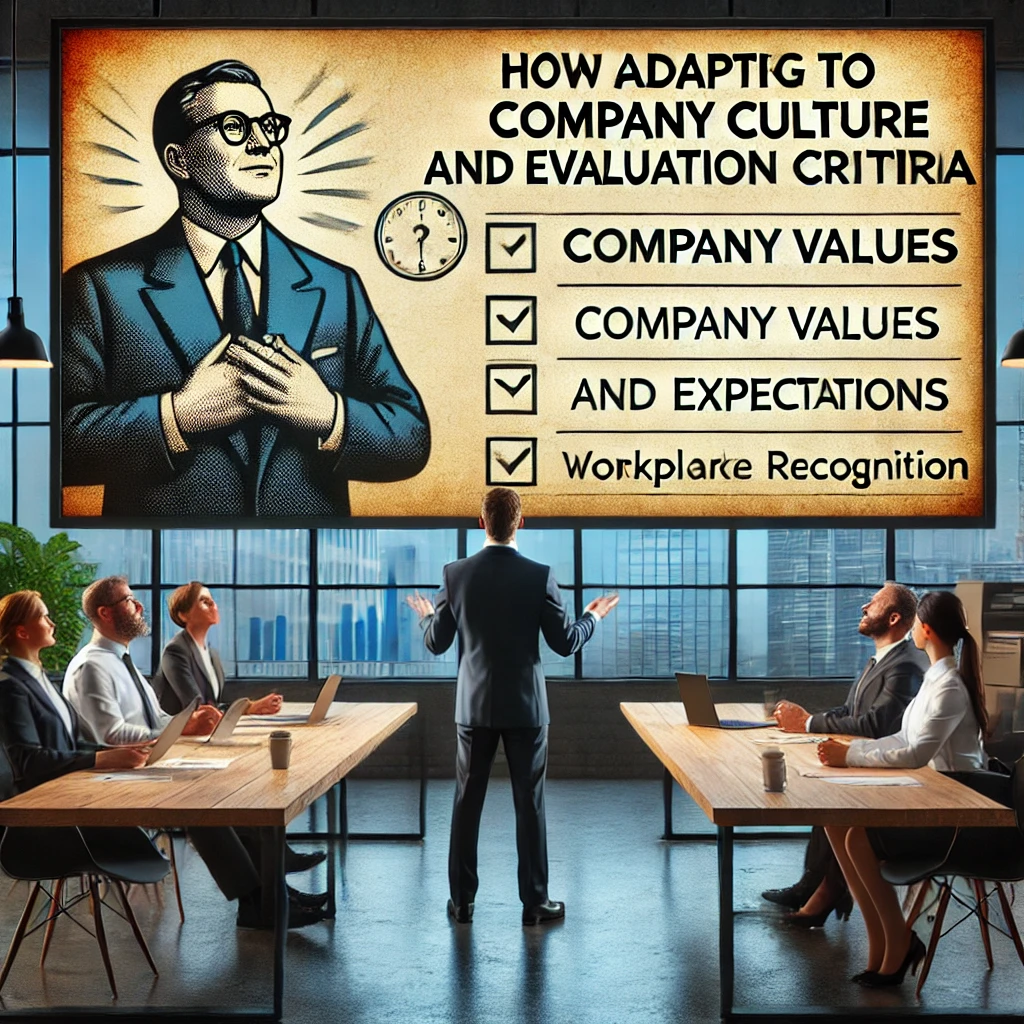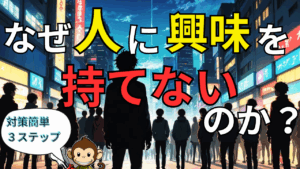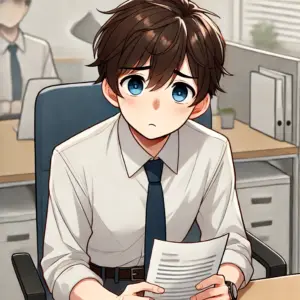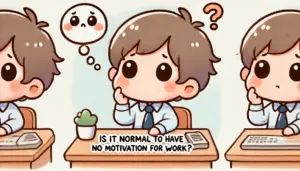職場の評価に納得がいかないあなたへ
「同じ仕事をしているのに、なぜあの人ばかり評価されるのか?」
「自分の方が努力しているはずなのに、上司に認められない…」
そんな風に感じたこと、ありませんか?
実は、上司に評価される人にはちゃんと“共通点”があります。
それは「派手で明るい人」「おしゃべりが得意な人」だけの特権ではありません。
むしろ、内向的でまじめな人こそ、ちょっとした“見せ方の工夫”だけで評価が大きく変わるんです。
かつて私も職場の上司から良い評価が貰えず、何が駄目なんだろう・・・。もっと頑張らないといけない・・・。と自分を責めて苦しんでいました。
今回はそんな生きづらいと感じていた私が、今では人生は楽しいと考えられるようになった考え方の1つ「上司に正しく評価されるための5つの視点」と、それに対して内向型でも取り組める対策をご紹介します。
- 【原因】そもそも上司に知られていないと評価されない
- 【対策】上司の評価するポイントを押さえる
- 【ポイント】数値などで見せる(見える化)
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして職場の人間関係で悩み苦しみ、辛かった思いをしてきました。
この記事では、「上司の評価に納得がいかない」と感じる読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
結論
評価とはその人の主観である。つまり自分の才能や努力の問題というわけじゃない。「伝え方」と「届け方」を変えるだけで評価は変わる。
評価の仕組みを理解し、それに沿った行動をすることで、嫉妬する立場から、正しい評価をされる側へシフトすることが可能です。
【なぜ?】評価される人とされない人の違い

✅ 評価される人の特徴
- 目立つ成果を上げ、上司に適切に報告する
- 会社の方針や上司の考えを理解し、それに沿った行動をする
- チームの雰囲気を良くし、協力関係を築く
- 社内外に影響を与える行動をしている
❌ 評価されにくい人の特徴
- 仕事はしっかりこなすが、成果をアピールしない
- 自分の価値観で仕事をしてしまい、上司の期待とズレる
- 上司との関係が薄く、普段の会話が少ない
- 「頑張っていれば認められる」と考えている
一言でまとめると
評価される人は「伝わる努力」をしている人で、評価されにくい人は「伝わるはず」と思っている人と言えます。
【なぜ?】上司が評価するポイントを知ろう

1. 目に見える成果を出している
- 「結果がすべて」と言われるが、実際は「見えやすい成果」が重要
- 定量的な数字(売上、コスト削減、効率化)で示せる仕事ほど評価されやすい
- 同じ努力でも、成果を「伝わる形で示せるか」どうかで評価が変わる
- 例:「○○プロジェクトでコストを15%削減し、年間100万円のコストカットを達成した」
2. 上司の求めることを理解している
- 「上司が評価するポイント」=「会社の目標」に合っているか
- 例:「売上重視の会社なら、目標達成率が評価基準になる」
- 上司が最も気にしているKPI(重要業績評価指標)という評価の軸を把握することが重要
- 上司の「お気に入り」になる人は、単に気に入られているだけではなく、上司の期待に応えている場合が多い
3. 発信力がある(自分の成果をうまくアピールできる)
- 「成果を出しても、上司が知らなければ評価されない」
- 報告・プレゼン・会議での発言が評価につながる
- 「私はこれだけの成果を出しました」と伝えることが重要
- 「頑張っていれば、誰かが見てくれる」という考えは危険
- 週1回の上司への進捗報告を習慣化するだけでも評価が変わる
4. 人間関係をうまく築いている
- 「上司との関係が良い人ほど評価されやすい」
- 飲み会・雑談・社内での立ち回りも意外と大事
- 上司に「扱いやすい部下」と思われることがポイント
- 「あの人と一緒に仕事をしたい」と思わせることが重要
- 例:「○○さんは仕事もできるし、コミュニケーションもうまいから頼りになる」と上司に思わせる
5. 会社の文化・評価基準に適応している
- 「会社の評価制度に合った働き方をしている」
- 例:「リーダーシップ重視の会社では、発言力のある人が評価されやすい」
- 会社が求める価値観に合わせるだけで、評価が大きく変わることがある
【実施リスト】対処方法5選
① 見える成果を“数字”で伝える
評価されるのは「がんばったこと」より、「伝わる成果」。
たとえば「いつも丁寧に対応しています」ではなく、「問い合わせ対応時間を平均5分短縮しました」と数字で伝えるだけで、印象がまるで変わります。
対策
- 日々の成果をメモ
月1で「自分の成果メモ」を残しておく(スプレッドシートでもOK) - 数値や実績で説明すると説得力がアップ
「数字で言い換える」練習をしておく(例:削減、改善、件数、回数) - 数字に言い換える習慣をつける
例:「○○のミス対応件数が月5件→1件に減りました」
② 上司が大事にしている“KPI(評価軸)”を知る
評価される人は、「上司の気にしているポイント」を押さえています。
上司=“採点者”です。自分が得意な種目だけ頑張っても、採点対象じゃなければ点はもらえません。
対策
- 上司の口グセ、よく聞くワードをメモる
評価される人は「採点者が何を見てるか」を知っている(「スピード感」「利益率」「効率」などメモ) - 週1の報告で、そのキーワードに関連づけて話す
上司が重視している基準を意識して動いている(例:「売上目標への貢献として、○○を意識して動きました」)
③ 成果を「ちゃんと伝える」力を育てる
「がんばっていれば誰かが見てくれる」は残念ながら通用しない時代。
特に内向型の人は、自分の成果を“黙って受け入れられる”と思いがちですが、実は伝え方も仕事のうちです。
対策
- 週1の「進捗+成果」を上司にチャット or 口頭で報告
評価=“気づいてもらう力”でもある。- ポイント:「私は○○をやりました」→「○○という結果が出ました」とゴール型で話す
- ポイント:話すのが苦手な人は、短く箇条書きでまとめておくと安心
④ 人間関係を“上手に”築く
評価される人は、「一緒に仕事しやすい人」です。
飲み会や雑談が苦手でも、ほんの少しの気づかいで「信頼されやすい人」になれます。
対策
- 仕事中の「ありがとう」「助かりました」を忘れず伝える
「一緒に仕事したい」と思わせる人は評価されやすい - 上司の言ったことを少し復唱する
派手な社交性よりも、“扱いやすさ”や“安心感”が鍵。(例:「わかりました、“週内に対応”ですね」)
⑤ 会社の“文化や評価軸”に合わせる
会社によって「評価されやすい人」は違います。
たとえば、「自分の意見をしっかり言う人」が評価される会社もあれば、「調和を保つ人」が評価される会社もあります。
つまり、「あなたがダメなんじゃなくて、合っていないだけ」のこともあるんです。
対策
- 「評価されてる人」を3人思い出して、共通点を観察する
評価される行動は、会社によって違う。「あの人はこうしてる」を真似するところからスタート - もし評価基準が合わない会社なら、環境を変えるのも選択肢
自分の働き方が評価されない会社なら、見切りをつけることも大切だと私は考えます。
私自身の体験として、20~40歳の間に5回以上転職を繰り返してきました。様々な理由で転職していますが、最後に転職した時は当時勤めていた会社に「見切りをつけて」転職しました。転職に関する考え方は人それぞれありますので考え方の一つとして参考にしてください。
ポイント「嫉妬」ではなく「学び」に変える
- 「あの人はなぜ評価されるのか?」→ その行動を観察し、取り入れる。
- 成功者を観察することは、評価を得るための最短ルート。
🔧 保全士的に言うと?
上司の評価とは、“検査工程”のようなもの。
成果(製品)がどれだけよくても、検査ラインに正しく乗せなければ合格印はもらえません。
- 伝えない成果=ラインに流れていない部品
- 数字のない成果=品質ラベルのない製品
- KPIに合っていない努力=別部門用の仕様
どんなに努力して頑張って作った完璧な製品でも検査ラインに乗らないことには何も評価されません。
つまり、「ちゃんと届けて、ちゃんと見せる」ためのライン調整=工夫が評価を変えるカギなのです。
体験談

上司の評価とは会社の評価制度を基準にしつつもそれ以外は個人的な判断が大きなウエイトを占めており、成果を数字で示せるかどうかなど上司の目に留まらなければその判断すらできません。また大企業であれば評価Aを2期連続で取らなければ昇格・昇進できないなどしっかりした基準があり、そうでなければ推薦で昇格・昇格を決めるケースがほとんどです。
記事を書いた本人
私の場合はそれほど大きな企業では無かったため、仕事が人についており、私がやっている業務を上司が把握しきれておらず、半年に1回ある面談では部署に合った今期の目標を何となく決めているだけの状態でした。
その為、結果としては自分の給与が低い、昇格できないという状況で、その全てを「部下の行動を把握も出来ていない上司のせい」にしておりました。
ですが今回書いた記事の内容である、「上司に正しく評価されるための5つの視点」を押さえた行動を実践、特に自分の業務内容の範囲や計画内容、実施して得た効果などをまとめて提出するように行動をしました。
上司の反応としては良い反応が返っており、上司自身としては自分の部署の仕事内容が理解でき、上層部に聞かれても答えれると喜んでいましたし、私に関して「そんなところまでやっていたのか」と驚かれました。
それからは聞かれてもいないのにこちらから毎週進捗を報告する「手のかからない成果を上げる部下」として「評価」してもらえました。
そして最終的にはいつの間にか上層部に対して昇格どころか昇進を推薦してくれており、無事昇進することができました。
この体験談のポイントとしては、業務の内容自体は何も変化しておらず、ただ上司に分かりやすいように効果を見える化して情報共有しただけという点です。つまり上司は見えていなかったので見える範囲で「評価」していたわけです。
 ひろのぶ
ひろのぶただまぁ結局のところ最終的に私は別の会社に転職をしています。
これは私自身に目標が出来てしまった結果の行動ですので割愛しますが、この記事の経験は私を大きく成長させてくれたと思っています。
関連記事
まとめ
重要なポイントとしては下記になります。
- 評価される人は「成果を出す+アピールする」伝わる努力をしている
- 「頑張る」だけでは評価されない。伝え方と戦略が重要
- 「上司に正しく評価されるための5つの視点」を意識する
- 「上司が何を求めているか?」を理解することが大切
- もし評価が不公平すぎるなら、環境を変えるのもアリ
- 評価されるために、嫉妬するのではなく学びに変える
- ① 見える成果を“数字”で伝える
→ 数値や実績で説明すると説得力がアップ - ② 上司が大事にしている“KPI(評価軸)”を知る
→ 上司の口グセ、よく聞くワードをメモる - ③ 成果を「ちゃんと伝える」力を育てる
→ 週1の「進捗+成果」を上司にチャット or 口頭で報告 - ④ 人間関係を“上手に”築く
→ 仕事中の「ありがとう」「助かりました」を忘れず伝える - ⑤ 会社の“文化や評価軸”に合わせる
- → 評価される行動は、会社によって違う
最後に
今回の記事を読んで頂くことで評価に関する悩みを少しでも解消し、仕事や生活を前向きに進めるための参考になれば幸いです!
ここまで読んでくださってありがとうございます。
このサイトでは私自身の知識、経験を元に様々な現実の問題から脱出する為の方法を書いていますので宜しければ今後もぜひご覧になって頂ければ嬉しいです。
それではまた。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。