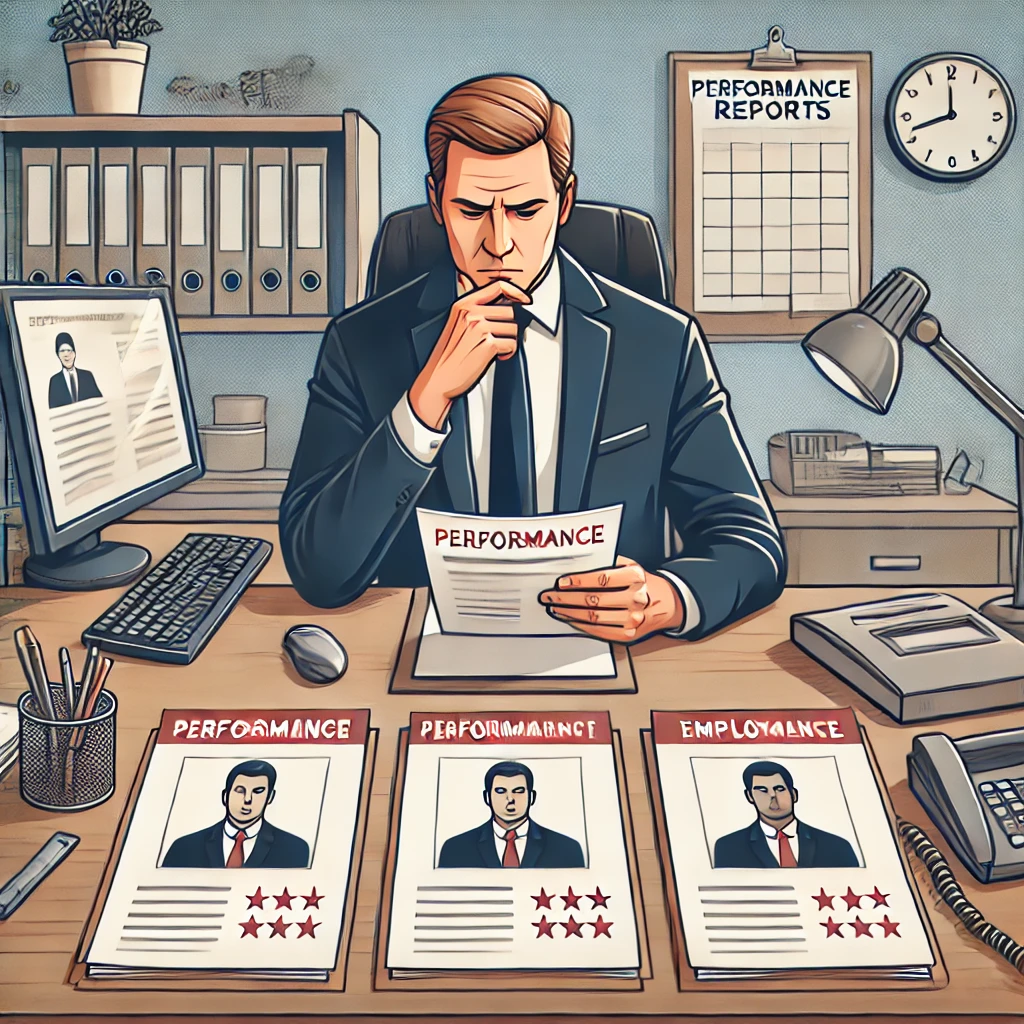職場の評価に納得がいかないあなたへ
「なぜAさんは評価されるのに、自分は評価されないのか?」
上司によって評価基準が違うと感じたことはありませんか?
職場の評価は、上司の価値観や会社の文化によって大きく変わります。ですので同じ仕事をしていても、上司のタイプによって評価のポイントが異なります。
かつて私も職場の上司から良い評価が貰えず、何が駄目なんだろう・・・。もっと頑張らないといけない・・・。と自分を責めて苦しんでいました。
今回はそんな生きづらいと感じていた私が、今では人生は楽しいと考えられるようになった考え方の1つ「上司のタイプ別評価基準5タイプ」をご紹介します。
- 【原因】評価の判断基準は主観が混じる
- 【対策】自分の上司のタイプを理解し、それに適応する
- 【ポイント】「どうすれば評価されるか」を考えること
記事を書いている人
記事を書いている私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして職場の人間関係で悩み苦しみ、辛かった思いをしてきました。
この記事では、「上司の評価に納得がいかない」と感じる読者のみなさんに向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、ストレスを軽減し、より快適に働けるようになるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
結論
評価を行う上司のタイプを見極めることが評価アップの第一歩! タイプごとに評価されるポイントが違うので意識して自分の仕事の「見せ方」を工夫することで評価を上げることが可能になります。
ですので現状で評価されないなら、上司の評価基準に適応する方法を試すことで現状を変えることができるかもしれません。
「評価されない」と嘆くのではなく、「どうすれば評価されるか」を考えることが大切です。
上司の評価基準を理解し、それに沿った行動をすることで正しい評価を受けることが出来ると言えます。
【なぜ?】評価される人とされない人の違い

✅ 評価される人の特徴
- 目立つ成果を上げ、上司に適切に報告する
- 会社の方針や上司の考えを理解し、それに沿った行動をする
- チームの雰囲気を良くし、協力関係を築く
- 社内外に影響を与える行動をしている
❌ 評価されにくい人の特徴
- 仕事はしっかりこなすが、成果をアピールしない
- 自分の価値観で仕事をしてしまい、上司の期待とズレる
- 上司との関係が薄く、普段の会話が少ない
- 「頑張っていれば認められる」と考えている
一言でまとめると
評価される人は「伝わる努力」をしている人で、評価されにくい人は「伝わるはず」と思っている人と言えます。
上司が評価するポイントを知ろう
上司の方が評価する際にポイントとなる項目として下記が考えられます。
- 1. 目に見える成果を出している
- 2. 上司の求めることを理解している
- 3. 発信力がある(自分の成果をうまくアピールできる)
- 4. 人間関係をうまく築いている
- 5. 会社の文化・評価基準に適応している
今回の記事では「2. 上司の求めることを理解している」に対して、そもそも上司のタイプによって、求めていることが違うというのがポイントになります。
関連記事
上記5項目「上司に正しく評価されるための5つの視点」ついて解説をしている記事が下記にありますので良ければご覧ください。
5タイプに分類できる理由
上司のタイプを5つに分類できる理由は、評価基準の多様性と個人の価値観にあります。上司はそれぞれ異なる価値観や経験、会社の目標に基づいて部下を評価します。そのため、評価されるためには上司の特徴や関心事を理解し、アプローチを調整することが必要です。
それぞれの上司は、以下のような要素に重きを置いて評価すると考えられます。
- 成果重視の上司は、「結果」が最重要であり、数字で示せる成果を求めます。
- プロセス重視の上司は、どのように結果を出すか、その過程を大切にします。
- 人間関係重視の上司は、職場の雰囲気やコミュニケーションを重視し、協力姿勢を評価します。
- 現場重視の上司は、実務能力や現場での行動力を見て評価します。
- 保守的な上司は、会社のルールや安定した業務の進行を重視し、変化を避ける姿勢を求めます。
これらの違いを理解し、自分が評価されるための方法を上司のタイプに合わせて工夫することで、評価アップが可能になります。
自分の強みを活かしながら、どのタイプの上司にどうアプローチすべきかを見極めることが、評価に繋がると考えられます。
数字重視の「成果至上主義」タイプ

特徴
- 数値で測れる成果を最重要視する
- 売上・コスト削減・業務効率化など、明確な数値をもとに評価する
- 「結果がすべて」と考えるため、プロセスにはあまり関心がない
評価されるポイント
✅ 数値で示せる成果(売上、コスト削減、業務改善など)
✅ 明確なデータを使った報告(エビデンス重視)
✅ 目標を達成する能力
プロセス重視の「マネジメント型」タイプ
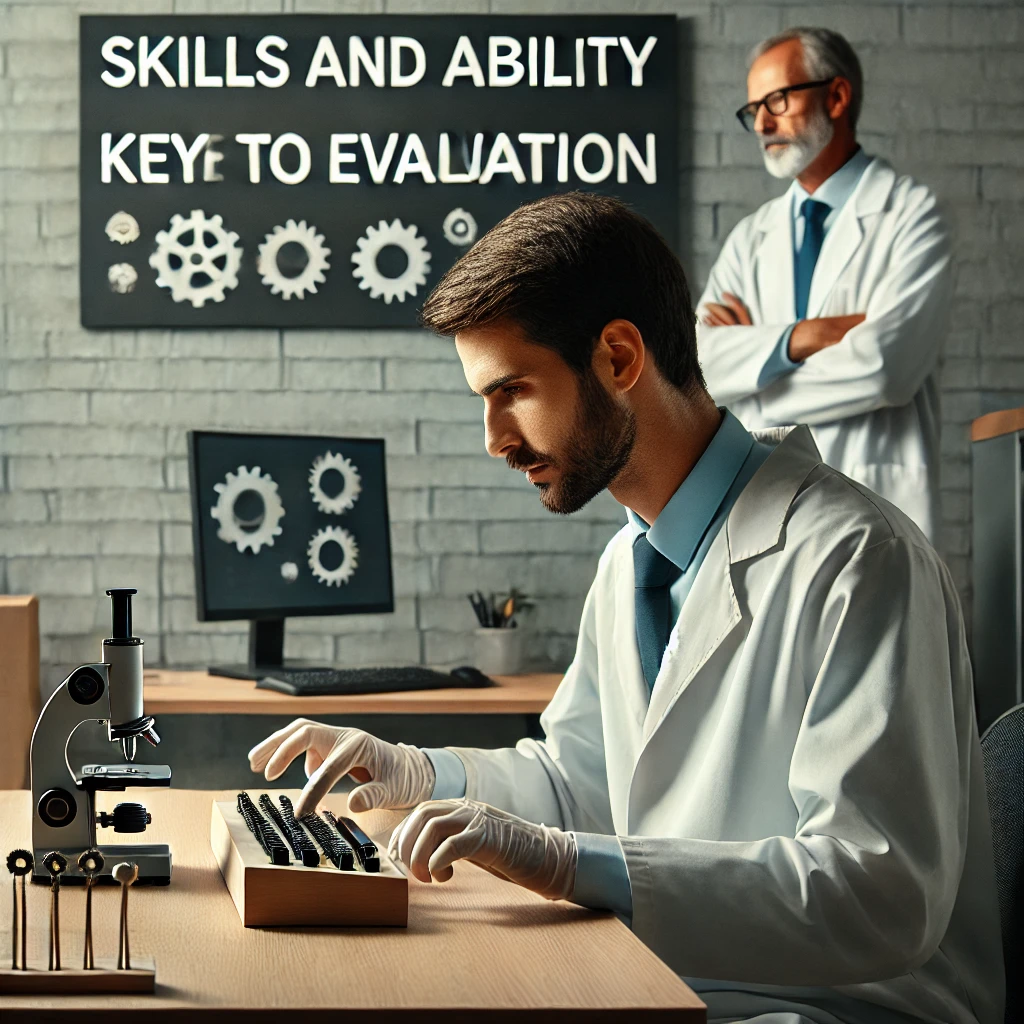
特徴
- 成果よりも、どのように達成したかを重視する
- チームワーク・協調性・リーダーシップが評価のポイント
- 部下の成長やプロジェクト管理能力を見ている
評価されるポイント
✅ チーム内での協力・リーダーシップ
✅ プロジェクトの進捗管理と適切な対応
✅ 部下の育成・チーム全体の成長に貢献
人間関係重視の「コミュニケーション型」タイプ

特徴
- 雑談や信頼関係を大切にする
- チームの雰囲気や対人関係を重視
- 親しみやすい部下を評価しがち
評価されるポイント
✅ 上司との良好な関係(雑談・コミュニケーション)
✅ チームワークや協力姿勢
✅ 職場の雰囲気を良くする貢献
現場主義の「実力主義」タイプ
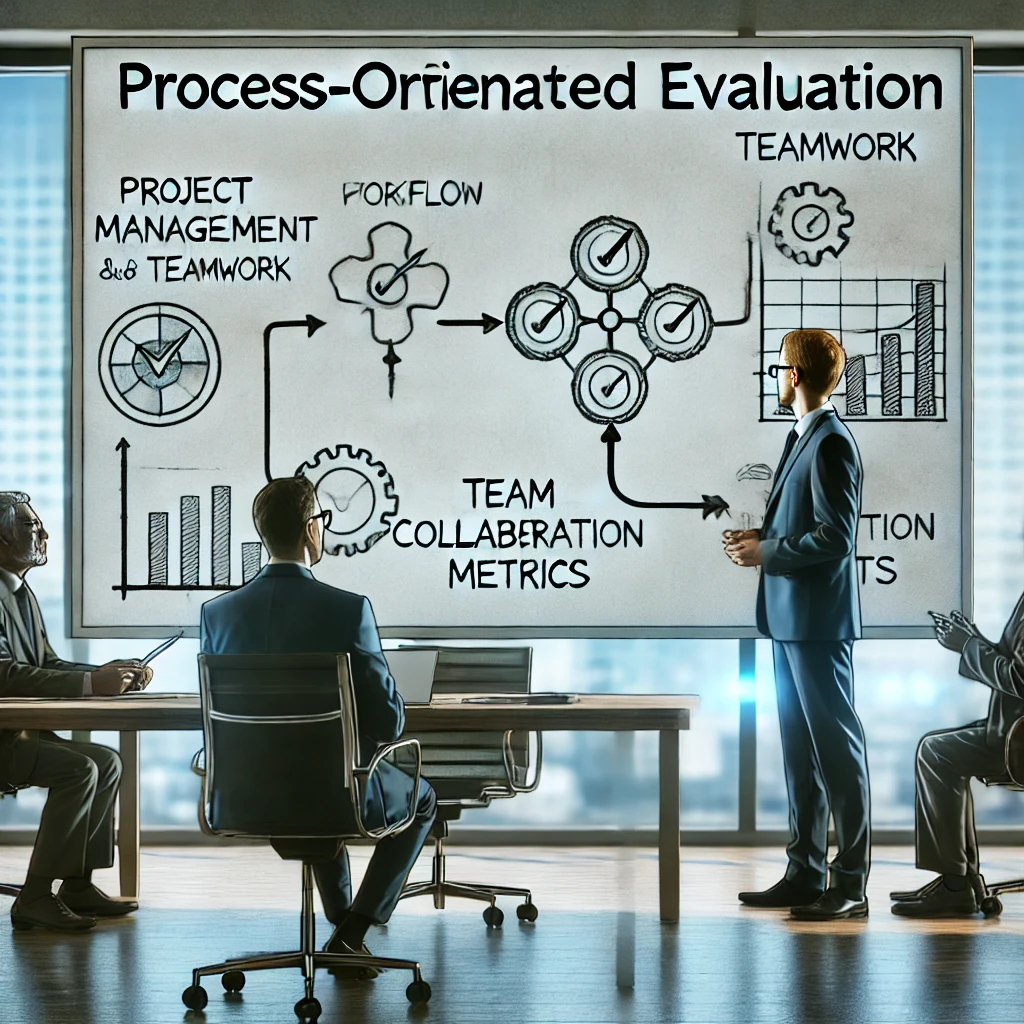
特徴
- 現場での行動力・スキルを評価する
- 経験豊富な職人気質の上司に多い
- 実績やスキルをベースに判断する
評価されるポイント
✅ 高いスキル・実務能力
✅ 自主的に動き、問題を解決する能力
✅ 現場での信頼度
保守的な「上層部重視」タイプ

特徴
- 会社のルールや慣習を重視する
- 上層部の意向に忠実で、安定志向が強い
- 変化を嫌い、従来のやり方を守る
評価されるポイント
✅ 会社のルールや方針に従う姿勢
✅ 上層部からの評価が良い(社内の人間関係)
✅ トラブルを起こさない、無難な行動
【実践リスト】具体的な対策3ステップ
①「上司の地図」を知る(価値観のリサーチ)
上司の口グセや判断基準、過去のフィードバックを思い出してみてください。
- よく言う言葉 → 例:「結論から話して」「とりあえずやってみて」
- 強く反応するポイント → 「慎重すぎる」「もっと早く進めてほしい」など
これらは、上司の価値観=“大事にしていること”のヒントになります。
② 自分との違いを冷静に整理する
次に、自分が大事にしている価値観と照らし合わせてみます。
- 上司:スピード重視/結論先行
- 自分:丁寧さ重視/背景を説明したい
このように違いがはっきりすると、「なぜ通じないのか?」が見えてきます。
ポイントは、「違うけど、どちらも正しい」と認めること。
ここで感情的になると、「なんでわかってくれないの?」という思考ループにハマりがちです。
③ 伝え方・接し方をチューニングする
相手の価値観に“一部合わせる”ことで、関係はぐっとラクになります。たとえば…
- 数字重視の上司には「感覚よりもデータで」
- プロセス重視の上司には「今、何をやっているかを」
ここでのポイントは、“自分を全部変える”のではなく、**「相手が受け取りやすい形に整える」**ことです。
各タイプ別対応
✅ 「数字重視の上司」には、成果を数値で報告する習慣をつける
- 定量的なデータをまとめ、週1回の報告を徹底
- 目標達成率や成果をグラフやリストで見せる
✅ 「プロセス重視の上司」には、進捗を細かく報告する
- 仕事のやり方やプロセスの工夫を伝える
- チームワークやリーダーシップをアピールする
✅ 「コミュニケーション重視の上司」には、積極的に会話を増やす
- 雑談を通じて関係性を深める
- 社内イベントやランチに参加する
✅ 「実力主義の上司」には、専門スキルを磨く
- 自分のスキルを証明できる成果を示す
- 資格取得や技術向上を継続する
✅ 「上層部重視の上司」には、社内ルールや慣習を理解し順応する
- 会社の価値観や上層部の意向を把握する
- 上層部が求める理想の社員像を研究する
この感情を“保全士的に例えると?”
もし、この感情を“保全士的に例えると”どうなるでしょうか?
上司との関係は、まるで工場のライン作業に似ているかもしれません。
あなたが伝えたい「意図」や「情報」は「製品」で、それをしっかりと「出荷」するためには、どのラインで、どんな手順を踏むかが大切です。上司はその「出荷先のお客」のようなもので、製品(情報)が正しく処理されるように機械が動きます。
しかし、上司の「求める製品」がA・B・Cと多々あり不明確だと、製品良品でもいらないものとして、受け取り拒否になってしまいます。
普段はスムーズに流れるコミュニケーションも、少しでもズレがあると問題が起こります。もし、「意図が伝わらない」と感じたら、それは求める製品が違うのかもしれません。
もしくは製品は間違っていないが、製造するラインの中で何かがうまくいっていない品質が落ちているサインかもしれません。そんなときは、まず自分が伝えたことを振り返り、フィードバックをもらって、次回はもっとクリアに伝える工夫をしてみてください。
体験談

上司のタイプに合わせた行動というのは上司に媚びていると思われがちですがそうではなく、会社なのですから組織の一員として上司に部下が合わせることは当然のことになります。ですが自分の意思を曲げろというわけではなく、あくまでもアピールの方法を変えるということです。
結果として自分の強みが上司と嚙み合わない可能性はどうしても出てきます。残念ながら組織では上司優先ですので上司が変わることはなく、自分が対処を工夫するしかありません。
ですが上司は上司で「部下に媚びるな、部下に合わせて変わるな」など指導されている場合もあります。人と人の相性ですので悩みがちですが、諦めて部署移動や転職などの選択も時には必要と私は考えます。
記事を書いた本人
私の場合は長年特に評価されることも無く、昇格・昇給もしていませんでした。ですがこの記事に書いている上司のタイプというものに注目して分析してみたところ、「プロセス重視の上司」ということが分かりました。
そして自分が今までは行っていた業務で、基本的には問題があった時にだけ報告・相談をしていたのですが、これでは「問題を自分で解決できないし、問題がたびたび起こる人物」という印象になってしまっていました。
ですが実際には案件100件に対して問題は1件など低確率で起こった問題だったのです。つまり普段の業務プロセスをしっかり報告していないがばかりにその1件に焦点を当てた評価をされていたということだと考えられました。
対策としては進捗を細かく報告することで、案件の99件が進捗に遅れも問題も無く、自分なりに改善をしているなどプロセスを見てもらい、わずかにある1件の問題も上司としっかり連絡・相談ができる「任せられる人物」と「評価」してもらうことが出来るようになりました。
結果として上層部に昇進を推薦していただき、昇進することができました。
まとめ
重要なポイントとしては下記になります。
- 上司のタイプを見極めることが評価アップの第一歩!
- タイプごとに評価されるポイントを意識する
- 自分の仕事の「見せ方」を工夫することで評価を上げることが可能
- 評価されないなら、上司の評価基準に適応する方法を試す
- 評価が適正でない場合は、転職や環境を変えることも選択肢の一つ
- ①「上司の地図」を知る(価値観のリサーチ)
→ 怒りは自分を守るためのエネルギー。受け止めることで暴走しにくくなる - ② 自分との違いを冷静に整理する
→ 深呼吸・冷水・ストレッチで交感神経→副交感神経へ切り替え - ③ 伝え方・接し方をチューニングする
→ 感情を感じながらも、現実的なベスト行動を選ぶ2段階思考 - 各タイプ別対応
→ 「数字重視の上司」には、成果を数値で報告する習慣をつける
→ 「プロセス重視の上司」には、進捗を細かく報告する
→ 「コミュニケーション重視の上司」には、積極的に会話を増やす
→ 「実力主義の上司」には、専門スキルを磨く
→ 「上層部重視の上司」には、社内ルールや慣習を理解し順応する
📩 最後に:あなたに伝えたいこと
上司を変えることはできなくても、上司に“合わせる視点”を持つことで、評価は必ず変わります。
「自分の価値を正しく伝える技術」は、あなたの武器になります。
今日から少しだけ、“伝え方”と“見せ方”を整えてみませんか?
「あなたらしさを活かして、“上司に届く伝え方”を見つけよう」
あなたがこの記事を読んで、上司からの評価がなぜ得られないのか、そして自分が悪いと責めなくてもいいと知って、自分のやりたいことや幸せに目を向けられる生活をする手助けになっていれば嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。