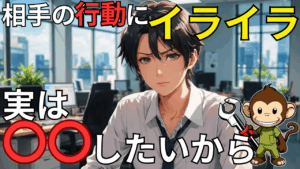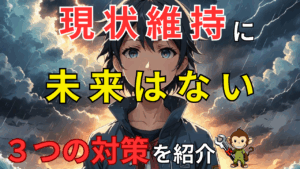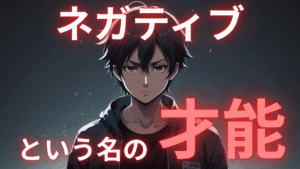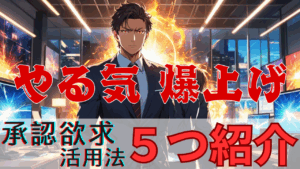仕事でストレスを溜め込んでしまっているあなたへ
「仕事や人間関係で日々ストレスを溜めていませんか?」
仕事で疲れて家に帰ってゴロゴロして気付いたら寝ており、また出勤の毎日。休日は普段の疲れを癒す為に家でゴロゴロして遊びに行く元気もない。そんな生活になってしまってはいませんか?
実は私自身がまさにそんな生活をしており、もっと人生を楽しみたいけどストレス疲れでそんな元気全くでないしこんな自分が嫌になる。
そんな生きづらいと感じていた私がストレス疲れが無くなり、人生は楽しいと感じられるようになった方法を紹介します。
- 【対策】日々の小さな習慣を変えることで、メンタルの強さは育てられる。
- 【原因】思考の癖がストレスを増やしてしまう
- 【ポイント】「ストレスを減らす」だけでなく、「ストレスを溜めない状態」を作ることを意識しよう!
記事を書いている人
私自身は企業に勤めるサラリーマンとして現在約40歳までの年月を過ごしてきており、その経験の一つとして日々の業務に追われ大変苦しい思いをしてきました。
ですが記事にある対策を実施することで、現在は昔であればストレスだったであろう事も全くストレスと感じなくなった為、仕事が楽になり、以前より人生が楽しく思えるようになることができました。
この記事では、「仕事のストレスを溜め込んで困っている人」に向けて、理屈と現実重視の世界で生きてきた元“機械保全士”の私が、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点で、前向きに生きるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。
結論
ストレスはあって当たり前、その都度解消するものであると思っている方が多いかもしれませんが、可能ならストレスをそもそも発生させないことが大切だと私は考えています。
そんなの当たり前と思うかもしれません。ですがその当たり前が出来ていない人が私を含めて多いのが現実です。
私は元“機械保全士”という機械を直すことに特化した職種でしたので故障の「根本原因」から考えるクセがあります。
ですのでストレスに対して発生後の対処法ではなく、発生前の根本対策に力を入れました。
またストレスは「溜まったら解消する」よりも、そもそもストレスを「溜めにくい状態を作る」ほうが心身への負担が少なく、長期的に健康を維持しやすくなると考えられます。
もちろんストレスはゼロにはできませんが、考え方や習慣次第で溜まりにくくすることができます。
その為に必要なことは日々の習慣を見直し、ストレスを溜めにくいメンタルを作ることになります。
【なぜ?】:「ストレスが溜まりやすい人の特徴」
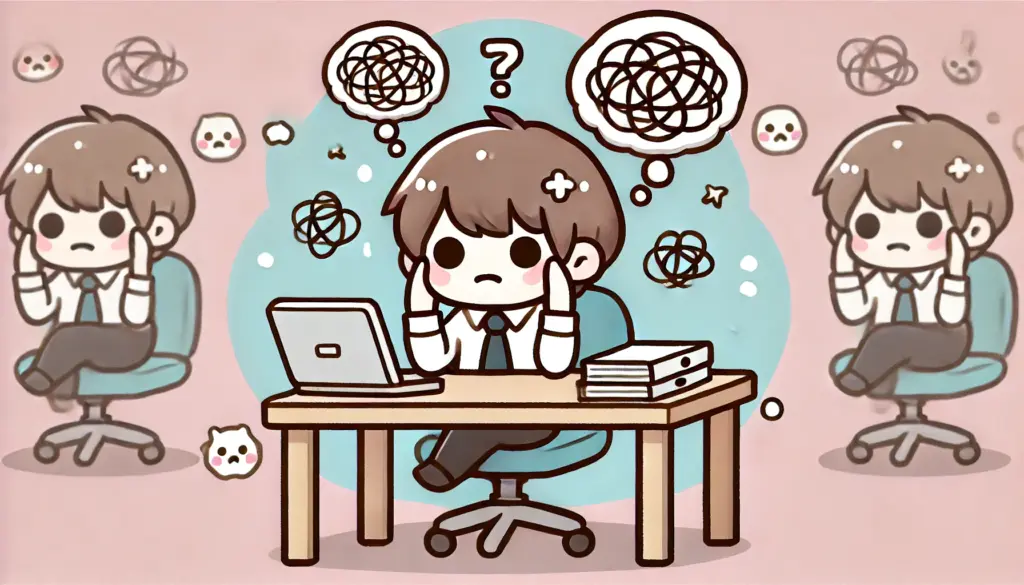
① 完璧主義になりすぎる
- ミスを過度に恐れる → 小さな失敗でも大きなストレスになる。
- 「100%を目指さなければいけない」という思い込み → 負担が増える。
② 他人の評価を気にしすぎる
- 「こう思われたらどうしよう」と不安になる → 常に周囲の目を気にする。
- 承認欲求が強いと、期待通りの評価が得られないとストレスが溜まる。
③ オン・オフの切り替えができない
- 仕事のことを引きずってしまい、リラックスできない。
- 休日でもスマホで仕事のメールをチェックしてしまう。
④ 物事をネガティブに捉えがち
- 「失敗=ダメなこと」と思い込むと、自己肯定感が下がる。
- 「自分は運が悪い」と感じると、ストレスを溜めやすくなる。
【具体例】:「ストレスを溜めにくい人の考え方」

ケース1:ミスしても必要以上に落ち込まない
→ 「ミス=成長のチャンス」と考える習慣をつける。
- 「ミス=学び」と捉え直すことで、ストレスを軽減。
- 反省はするが、自分を責めすぎない。
ケース2:他人の言動に振り回されない
→ 「自分でコントロールできること」に意識を向ける。
- 他人の評価ではなく、自分の成長にフォーカスする。
- 「他人がどう思うか」より「自分がどうありたいか」を重視。
ケース3:自分の感情をコントロールできる
→ 感情を言語化して整理する(メモや日記を活用)。
- イライラした時は、紙に書き出して冷静になる。
- 感情を客観視することで、ネガティブな気持ちに振り回されにくくなる。
【考え方】ワーク・エンゲイジメント

ワーク・エンゲイジメントとは仕事にポジティブな感情を持ち、充実している状態を指します。仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態ともいえます。
島津明人. (2010)によると、このワーク・エンゲイジメントが高い人は心理的苦痛や身体愁訴が少ないことが明らかにされているとあります。
つまりワーク・エンゲイジメントが高い人はストレスが少ないと言えます。
ワーク・エンゲイジメントが高い人
下記にワーク・エンゲイジメントが高い人の条件を記載していますが、簡単に言うと仕事や生活において「身体的・心理的負荷が少ない、目標設定・達成・成長する、自分で環境をコントロールできる、困難から回復する、肯定的な自己評価をする」となります。
仕事の資源
仕事の資源とは物理的・社会的・組織的な要因で下記になります。
- ストレッサーや身体的・心理的コストの低減
- 目標達成を促進
- 個人の成長や発達を促進
個人の資源
個人の資源とは目標設定・動機づけ・パフォーマンス・仕事や生活への満足感で下記になります。
- 自分を取り巻く環境をコントロールできる
- ストレスを跳ね返し、困難から回復する力
- 上記に関連する肯定的な自己評価
引用:島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.
https://doi.org/10.5058/stresskagakukenkyu.25.1
やるべきこと
上記のことから実践することとしては下記になると考えられます。
- ストレッサーや身体的・心理的コストの低減 ⇒ストレスを減らす環境作り
- 目標達成を促進 ⇒目標の設定・達成
- 個人の成長や発達を促進 ⇒目標に対して成長
- 自分を取り巻く環境をコントロールできる ⇒他人軸ではなく自分軸で仕事
- ストレスを跳ね返し、困難から回復する力 ⇒ストレス耐性向上・感情のコントロール向上
- 上記に関連する肯定的な自己評価 ⇒自己評価する場を決める
これら内容に対しての対策内容が次になります。
【実践リスト】「ストレスが溜まらないメンタルを作る習慣」

①物理的・心理的にストレスを減らす環境を作る
- 「生活リズムを整える」
- 睡眠不足はストレス耐性を下げるため、7時間以上の睡眠を確保する。
- 「情報のシャットアウトを意識する」
- SNSやネガティブなニュースを見すぎると、ストレスを受けやすくなる。
- 「無駄な人間関係の整理」
- 自分にとってプラスにならない関係は、適度な距離を取る。
②「目標を決める」(目標設定を習慣化)
- 目標を達成するためには、明確で達成可能な目標を設定することが重要です。
- 例: 「3ヶ月以内に毎朝30分間、ランニングをする」など、具体的で測定可能な目標にすることが大切です。
- 小さなステップに分ける
- 例: 目標が「3ヶ月以内に健康的な体を作る」なら、毎週運動メニューを決め、食事計画を立てるなど、日々やるべきことをリスト化します。
- 進捗をチェックし、修正する
- 例: 毎週日曜日に進捗を確認し、できたことを振り返り、できなかったことがあれば改善策を考えます。
③「思考のクセ」を鍛える(成長に目を向けた捉え方を習慣化)
- 「自分を責める」ではなく「改善点を見つける」
- 例:「ミスした」→「この経験から何を学べるか?」と考える。
- 「なぜできなかったか?」より「どうすればできるか?」に目を向ける
- 問題の解決にフォーカスする習慣をつける。
④「他人軸」ではなく「自分軸」で考える
- 「自分の価値観」を明確にする
- 例:「私は◯◯を大切にしたい」と、自分の行動指針を持つ。
- 「他人の意見は参考にするが、最終的に決めるのは自分」と考える
- 「こう思われたらどうしよう」ではなく、「自分がどうありたいか」に意識を向ける。
- 「仕事をやらされる」ではなく自分の為と考える
- 仕事は強制と考えると「他人軸」でありコントロール不可能、そうではなく結果として自分の為と考えることで「自分軸」となり、コントロールできる。
⑤ストレス耐性を高めるルーティンを作る
- 「意識的に心を休める時間」を確保する
- 毎朝5分間の深呼吸や瞑想を取り入れ、メンタルを安定させる。
- 「ルーチン化」で精神の安定を作る
- 朝の散歩、ストレッチ、読書などをルーティンにすることで、ストレスに左右されにくくなる。
- 「楽しいこと」をスケジュールに入れる
- 週に1回は、純粋に楽しめる時間(趣味・運動・交流)を確保する。
⑥感情のコントロール力を高める
- 「怒り・不安・焦り」を言語化する習慣を持つ
- 例:「なぜ今、自分はイライラしているのか?」を紙に書き出す。
- 「マイナス感情に振り回される前に、一旦止まる」
- 例:イラッとしたら、6秒待つ or 深呼吸することで冷静になれる。
- 「ネガティブ思考」で自己否定するのではなく、肯定的な自己評価をする
- ポジティブに考える、もしくは客観的に考えることで少しでも良い点を見つける。
⑦肯定的な自己評価をする
- 成功体験を振り返り、自信を持つ
- 実践方法: 毎日または週に一度、自分が達成したことや良かったことをリストアップしてみましょう。その成果を認識し、自分を褒めることが自己評価を高めます。
- ポジティブな自己対話をする
- 実践方法: 毎夜、鏡を見ながら自分にポジティブな言葉をかける習慣をつけてみましょう。「今日の仕事は良かった」「反省点はあるけど80点は取れてる」といった自分に合ったフレーズが効果的です。
- 他人と比較せず、自分の成長を重視する
- 実践方法: 1ヶ月ごとに、自分がどれだけ成長したかを振り返り、目標に近づいていることに焦点を当てることで、自分の進歩を実感できます。
 ひろのぶ
ひろのぶ私が実践した内容になります。数は多いですが全部を一度に取り入れたわけではなく、少しづつスモールステップで行いました。
効果が出るまでに数か月はかかりましたので気長に取り組んで欲しいです。
【体験談】


記事を書いた本人
私の場合は業務の内容が人についてまわる場合が多く、一人で何でも業務を背負ってしまっており、また業務が他部署から回ってくる為、相手に意見を合わせてしまう癖がついているストレスが多い状態でした。
その為、人に頼ったりできずに無理がたたってミスをしてしまったり、その際にも自分を責めていたり、何か報われたいと他の人から見た自分の評価が気になっていたり、他部署の人からもこれ以上業務を増やされないよう悪印象を与えないように自分の発言をしないで言いなりの状態。
そしてそんな状態では上司からは「自分の意見が無いやつ」と見られて評価も上がらない悪循環に陥っていました。
ですが今回の記事の内容を実践することで「自分を責めるのではなく、改善点を見つけて」、「他人軸ではなく、自分軸で行動を決め」、「無駄な人間関係に神経をすり減らす」ことも無くなりました。
そこからは人の業務は人の業務で手伝うことはあっても自分で背負い込むこともせず、時には頼ることも増え、他人に左右されない自分の意見や行動をするようになり、自信を持って業務を行うことができるようになりました。
また業務をもっと楽にしようと考える余裕が生まれ、他部署に対してもっとこうしようと自分の意見を言うことも増えていき、お互いの部署にとって業務の手間というロスを少しずつ減らす効果が出てきました。
その結果、上司から評価が180°変わって「自分で率先して行動できる頼れる人材」と判断され、昇進することができました。
【まとめ】ストレスを溜めない状態を作ろう
重要なポイントとしては下記になります。
- ストレスは避けられないが、「受け止め方」を鍛えれば溜まりにくくなる。
- 日々の小さな習慣を変えることで、メンタルの強さは育てられる。
- 「ストレスを減らす」だけでなく、「ストレスを溜めない状態」を作ることを意識しよう!
最後に:あなたに伝えたいこと
この記事で言うストレスが溜まらないメンタルとは、メンタルを強くすることです。
これは自分を無理に変えるのではなく、自分を理解して自分自身をうまくコントロールすることです。つまりあなた自身を作り変えるというよりかは、本来の力を引き出しているというイメージです。
ストレスを溜め込まないメンタルは自分自身のポテンシャルを発揮する為に効果的で、結果として成果が出たりもします。そうでなくても純粋に楽に仕事がこなせるようになれば日々の生活は楽しむ余裕が生まれてきます。
あなたがこの記事を読んで、自分のやりたいことや幸せに目を向けられる生活をする手助けになっていれば嬉しいです。
ここまで読んでくださってありがとうございます。
関連記事(おすすめ)
ストレスの解消法
ストレスは溜めないにこしたことは無いですが、溜まってしまった場合は解消するべきです。その解消法について紹介をしている記事が下記にありますので良ければご覧ください。5分でできるリフレッシュ方法やサラリーマンの仕事の進め方改善など紹介しています。
このサイトが大切にしていること
このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 島津明人. (2010). 職業性ストレスとワーク· エンゲイジメント. ストレス科学研究, 25, 1-6.